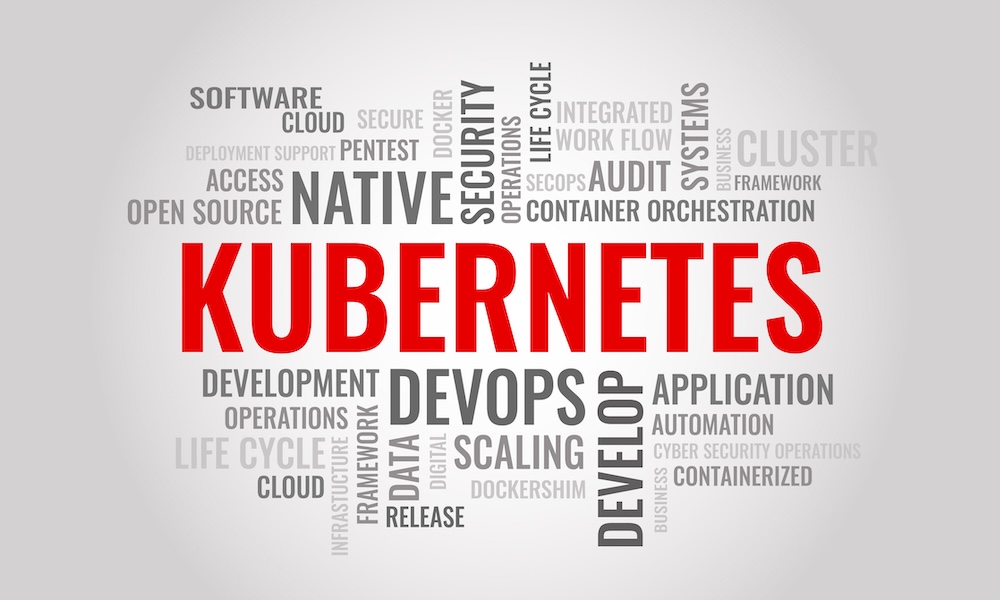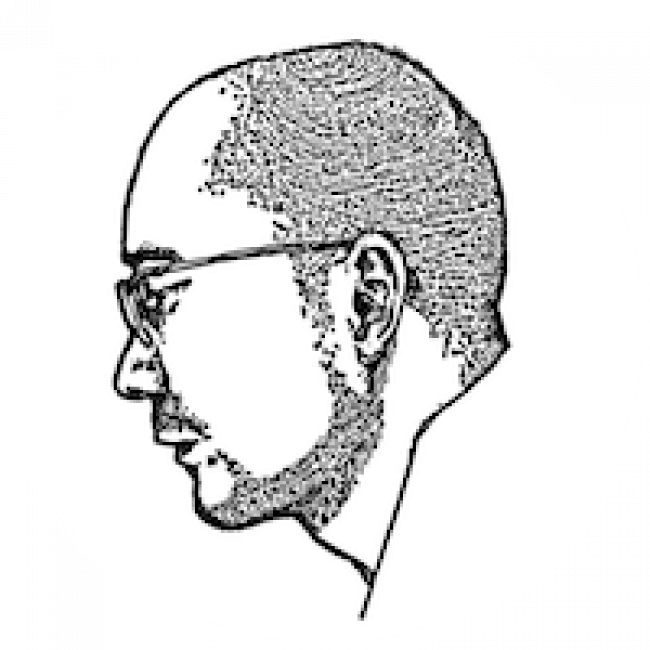なぜOSSの「コントリビューション」と「オープンソース活動」が重要なのか

はじめに
急速に変化し続ける社会や市場に対応するための、動的で拡張性の高いワークロードを実行する仕組みとして、クラウドネイティブ技術の「Kubernetes」が注目されています。最近では、Kubernetesは単に顧客ニーズに対応したサービスを迅速に提供し続ける基盤としてだけでなく、生成AIの学習・推論の基盤としての活用も進んでいます。国内の話題としては、2025年6月に日本で初めて「KubeCon+CloudNativeCon Japan」が開催され、約1,500名の参加者を集めるなど、日本でも大きな盛り上がりを見せています。
Kubernetesは2014年にOpen Source Software(OSS)として公開されて以降、世界中の8万人以上のコントリビュータによって開発され、現在では世界で2番目に大きなオープンソースプロジェクトになっています。OSSは単一の企業で管理・所有されていないため、プロジェクト・ソフトウェアを維持・改善するにはコントリビュータの維持・拡大が必要となります。これは主要なOSS共通の課題であり世界中で様々な取り組みがされていますが、日本でもKubernetesコミュニティへのコントリビューションへの参加の障壁を下げるために「Kubernetes Upstream Training Japan(KUTJ)」が2019年より継続的に開催されています。
本連載では、KUTJの講師6名が分担して、Kubernetesを例にOSSへのコントリビューションについての実践的な知識を紹介していきます。第1回の今回は、まずOSS・コントリビューションについて日立製作所の木村が解説し、続いてオープンソース活動を組織的に行うために必要なこと、オープンソースコミュニティとイベントについてNECソリューションイノベータの武藤が解説します。
OSSとコントリビューション
OSSとは
ざっくり言うと、OSSはソースコードが公開されており、使用・改変・再配布などが許諾されたソフトウェアの総称です。厳密な定義はOpen Source Initiative(OSI)が公開している「The Open Source Definition(OSD)」を参照してください。OSSは特定企業が管理・所有しているプロプライエタリソフトウェアとは異なり、有志の開発者のバグ修正・機能追加などのコントリビューションにより改善・維持されています。そのため、企業や組織の垣根を超えた世界中の人々のコントリビューションによって迅速に開発・改善され、大きなイノベーションを起こす可能性があります。一方で、コントリビューションが少なくなると改善・維持が困難となる側面があります。
なお、Kubernetesなどの大規模なOSSは、Cloud Native Computing Foundation(CNCF)のようなOSSのプロジェクトのガバナンスを維持する組織に管理され、複数の企業・組織が方向性を決め・利益を生み出し・再投資されることでプロジェクトの持続可能性を維持する仕組みを持っています。つまり、OSSはコントリビューションによって成り立っているソフトウェアですが、成功しているOSSは、多くの人や組織が「コントリビューションする価値がある」と思えるような代物になっているはずです(例えば、昨今の情勢からベンダーロックインされにくいソフトウェアの価値はさらに上がって来ているのではと思います)。
コントリビューションとは
まず「何がコントリビューションになるか」についてです。OSSへのコントリビューションで最初に思いつくのはコードを書くことだと思いますが、それ以外にも多岐に渡ります。例えば、ドキュメントの日本語翻訳・記載の追加や、issueを作成してバグ報告・機能追加の要望を出すこともコントリビューションになります。既にissueがある場合でも、追加の動作確認結果やユースケースの追加、別の実現案のコメントなどをすることもできます。もう少しコードに触れるコントリビューションとしては、自分で大きな機能のコードを追加する以外に、コードレビュー・リファクタリング・テストコード追加もあります。一方、コードから離れる方向では、イベントに参加して使い方・ユースケース・最新機能などを情報交換することや講演することもコントリビューションになります。コントリビューションのやり方は色々あるので、今、自分は何ができそうか・何がやりたいのか・何が求められているのか等で決めるのが良いと思います。
次に「何のためにコントリビューションするのか」についてですが、これも多岐に渡ります。また、個人として行うのか・企業として行うかの視点でも異なります。
個人としての目的は人それぞれですが、技術以外を含めたスキルアップ、社内外からの実績・技術力の認知、最新の技術動向の把握などが挙げられます。これが「実益(昇格・昇給・転職有利等)につながるから重要」と考える人も、単に知的好奇心のように「面白いと思ったから趣味としてやっている」という人もいるでしょう。また、もう少し広い視点で、世界中の人と知恵を持ち寄ってイノベーションを起こすことや、イノベーションを通して世の中に影響を与えることに価値を感じるかもしれません。
企業としての目的の詳細については後半に譲りますが、企業の活動の一環として個人がコントリビューションを継続的に行う場合は、企業と個人の目的やコントリビューションの方向性の一致が重要になります。継続的に企業からのコントリビューションへの投資が得られること、企業が必要とするコントリビューションのスキルを持ったエンジニアがその企業で維持できることの両方が鍵となるからです。
コントリビューションの障壁とその克服
OSSへのコントリビューションは、グローバルな活動である故に様々な障壁があります。ここでは、その代表的なものと克服法を紹介します(が、ここで言いたいのは「大変ですよ」とハードルを上げたいのではなく、「みんな同じ悩みを抱えた人なので、臆することはないです!!」ということです)。
- 時間的・空間的な距離:
- 課題: タイムゾーンが異なるためF2Fのコミュニケーションが困難。チャット・メール・GitHubコメントなどでの非同期なコミュニケーションとなることが多いため、レスポンスを得るための往復に時間がかかることが多い
- 克服方法の例: 焦ってもしょうがないので焦らない・他の人のタイムゾーンを合わせてリモート会議に参加する・KubeConなどのイベントでのF2Fの機会を活用する・非同期のコミュニケーションツールでの意思疎通の精度を高める等
- 文化や民族性の違い:
- 課題: 文化や民族性の違いによる誤解や認識の齟齬が発生する場合がある
- 克服方法の例: ステレオタイプによる誤解に注意する・違いを認識し誤解や認識の齟齬に気をつける・CNCFのCode of Conductを参考にお互いに包摂的で相手を尊重した行動をする(結果としてみんな良い人で気を遣ってくれるので、こちらも気を遣ってあげましょう)
- 言語の違い:
- 課題: 基本的に英語でのコミュニケーションとなるため、苦手意識があったり、考えや思いが伝わるのか不安になったりしがち
- 克服方法の例: 翻訳/文法チェック/生成AIなどのツールを活用する(非同期コミュニケーションが多いのがプラスに働く点)・シンプルな表現を心掛ける・絵文字(👍💯😀😆🙇)やチャット略語(ditto、nits、PTAL、WDYT、SGTM、IMHO等)を活用する・相手も英語ネイティブばかりでないことを認識する(分からないのは自分のせいだけではない可能性もあるし、相手も「自分が悪いかも」と思って分かろうとしてくれます)等
ここまでコントリビューションの様々な一般論を説明しましたが、「何かコントリビューションをしてみたい」という気持ちが生まれたら、とりあえずやってみるのがオススメで、その一歩を踏み出す後押しをすることがKUTJの目的となっています。
オープンソース活動を組織的に行うには
ここからは武藤さんにバトンタッチして、組織として・個人としての両面から、具体的にコントリビューションに取り組む際に役に立つ情報を語ってもらいます。この情報を参考に、まずは「最初の一歩」を踏み出してもらえればと思います。組織としてOSS利用、貢献、支援などのオープンソース活動を行っていくにはどうすれば良いか、といった観点で解説をしていきます。
オープンソースは、単に技術を利用するためのモノとしてのソフトウェアではなく、継続的に組織のイノベーションや競争力を高めるための戦略的な取り組みでもあります。欧州委員会によるレポートでは「OSS貢献が10%増加するとGDPが0.4〜0.6%増加する」とされており、マクロな経済的試算の上でも、その価値は膨大なことが分かります。欧州全体と一企業を比較するのは規模的に大きな開きがあるかも知れませんが、事業が複数になり、企業が大規模になるほど、同様の見方ができると思います。
OSSは組織内のほとんどのプロジェクトでも活用されており、コードベースにおけるOSSの占める割合は7割を超えると言われています(Synopsys社「OSSRA Report」など)。その無視できない分量で活用されているOSSの様々な価値を、オープンソース活動を通して十分に享受する組織的な戦略が重要になっています。
オープンソース活動は、個々の開発者が自発的に行うことも多いですが、組織として取り組むことでその価値や文化を組織力の1つとして育み、変化の激しいソフトウェア領域で継続的に取り組めるようにすることが重要です。
そのためには、個人任せや単発的な取り組みではなく組織の仕組みとして定着させ、これを運用する体制を整え、トップマネジメントから開発現場まで根付かせることが鍵になってきます。以下では、その主要な観点を整理します。
コンプライアンスとガバナンス
OSSを組織的に利用する際、まず直面するのがコンプライアンスの問題です。OSSのライセンスは多様で、著作権や特許の取り扱い、輸出規制などに注意する必要があります。OSSが他のOSSに依存していることも多く、OSS間の複雑な依存関係を明らかにした上で、それぞれのOSSに対するコンプライアンスを遵守しなければなりません。
複雑な依存関係は、OSSの脆弱性を覆い隠してしまうことも考えられます。依存関係をすべて明らかにすることは、セキュリティリスクへの対応でもあります。
国際的には「OpenChain」(ISO/IEC 5230)がOSSコンプライアンスの標準として広く利用されており、ライセンス遵守のためのプロセス整備や教育のベストプラクティスを提供しています。
また、セキュリティ面では「OpenSSF(Open Source Security Foundation)」が推奨する「Supply-chain Levels for Software Artifacts(SLSA)」や「Scorecard」などのベストプラクティスが活用できます。これらは特定ベンダーに依存しない公開情報であり、組織が中立的にOSSの利用を進める上での有効な参照点となります。
それだけでなく、ヨーロッパでは「Cyber Resilience Act(CRA)」が施行されたことで、利用しているOSSに問題が起きた際は解決しなければなりません。つまり、自らOSSへの貢献を行い、自ら解決する必要性が高まっているのです。
組織としてOSSプロジェクトに貢献する際には、提供する成果物に公開すべきではない知的財産が含まれていないか、輸出規制などの法的リスク、新たに結合する依存関係が持つライセンスの適合性など、様々なリスクに留意することが不可欠です。また、自社製品やサービスが利用するOSSの重要性、可用性、代替性、OSSプロジェクトの健全性、エコシステムの活性度などにより、どのOSSプロジェクトにどこまで依存し、どの範囲まで貢献するかという戦略的な判断も必要になります。
こうしたOSSの利用と貢献に関する組織内のルールや基本方針、オープンソース活動に関わる判断や評価に必要な情報収集と説明、教育、これらのガバナンスを効かせる運用体制が必要になってきます。
貢献の目的(事業やエンジニアの目標に沿った貢献)
組織的なOSS貢献は単なる「善意の活動」ではなく、さらに自組織や開発者個人の戦略や目標に資する活動であることが重要です。具体的には、以下のような戦略や目標です。
- 事業への直接的効果: 必要な機能の追加やバグ修正を還元することで、自組織の製品・サービスの品質や効率性を高める
- プレゼンスとブランド価値: 継続的なOSS貢献を通じて組織や開発者の名前が世界中の開発者コミュニティに認知され、採用やパートナーシップ形成にもつながる
- 技術力と人材育成: 開発者がグローバルな開発プロセスに参加することでスキルや経験を獲得し、人材の成長とキャリアアップを促進し、開発者個人のプレゼンス向上と合わせて極めて高い開発者満足度を獲得する。開発者満足度は組織とのエンゲージメントの向上に繋がり、人材を引き止める要因となる
- 社会貢献: SDGsに直接役立つOSSがあるだけでなく、オープンソースの差別禁止の精神はSDGsと共鳴する(LF)。国連はデジタル公共財を「SDGsの達成に役立つOSS、オープンデータ、オープンAIモデル、オープン・スタンダード、オープンコンテンツ」と定義(Wikipedia)しており、OSSへの貢献は組織として(特にIT企業としては最も王道)の業界貢献であり社会貢献と言える
オープンソース活動を「自組織の利益」「開発者満足度」「社会への貢献」の3方から捉え、これらのバランスを維持することが持続的な成功の鍵です。
Open Source Program Office(OSPO)
組織的にオープンソース活動を推進する基盤として「OSPO(Open Source Program Office)」の設立が有効であり、世界的に広がっています。OSPOはオープンソースに関する方針の策定、社内外への宣言や透明性の確保、開発現場への浸透と運用、コンプライアンス管理、定期的な活動の評価を担います。OSPOを通じて個人任せではなく組織的にオープンソース活動をマネジメントし、持続可能な取り組みにすることができます。
- 方針と指針の策定: OSSの利用・貢献に関する社内ルールを定義し、透明性を確保する
- 教育と啓発: 開発者にライセンスやセキュリティの知識を普及させ、適切なコントリビューションを促す
- プロセスの運用: 外部へのコード公開やパッチ提供をスムーズに行える社内手続きを整備する
- 評価と改善: 定期的にオープンソース活動の成果を振り返り、改善サイクルを回す
OSPOを立ち上げる際には、世界中のコミュニティが公開しているベンダーニュートラルなベストプラクティスを参考にできます。
参照すべきベストプラクティス例- TODO Group – 企業のためのオープンソースガイド
世界中のOSPO運営者による実践的なガイドライン集 - OSPO Alliance – Open Source Good Governanceハンドブック
欧州のメンバーが中心となり策定されたオープンソースガバナンスの包括的なハンドブック。ライセンス管理から戦略、組織文化への浸透まで網羅的に整理されており、欧州企業・行政機関だけでなく世界中の多様な組織が参考にできる内容になっている
これらのベストプラクティスを参照することで「自分の組織に合ったOSPOの形」を設計でき、属人的な活動に留まらず持続可能なオープンソース活動を実現できます。
しかしながら、こうした組織的な活動のための部署の設立や運用にはトップマネジメントの理解が必要になってきます。これは、組織的なオープンソース活動を始めるための最も困難な課題の1つとされています。これを克服するにはオープンソースの世界で自ら活躍したり仲間を増やすなどの方法がありますが、理解してもらい、あるいは説得するのは依然として時間と労力が必要な作業です。諦めないことが一番重要かも知れません。
オープンソースコミュニティとイベント
オープンソースの価値はソースコードだけでなく、それを育むコミュニティそのものにも大きな価値があります。OSSや技術はコミュニティを通じて成熟し、標準化され、参加する技術者や組織とともにエコシステムを形成し、持続的な発展を遂げていきます。そのため、組織がオープンソースに取り組む際にはコミュニティに参加し、イベントを通じて情報交換や協働を行うことが不可欠です。また、コミュニティメンバーとして外部からの目線に切り替えたとき、よりマクロでグローバルな潮流・動向など、新たな気付きを得られるでしょう。
グローバルなコミュニティ
オープンソースの世界では、ベンダーニュートラルな運営が重要視されます。例えば、Linux Foundation(LF)やCNCFは単一企業の影響を避け、広範な参加者による合意形成を行っています。こうしたコミュニティにおいては、透明性・ガバナンス・ドキュメンテーション・レビュー体制などが確立されています。こうした仕組みがOSSプロジェクトを持続可能かつ信頼できるものにしており、このようなコミュニティがホストするOSSであることは利用・貢献するOSSを選定する際にも有用な指針になります。
ベンダーニュートラルなコミュニティは、技術標準やエコシステムの形成も担っています。こうしたコミュニティに参加することは最新の技術動向を知るだけでなく、グローバルな議論の中で自らの声を届けること、つまり標準やベストプラクティスの策定に影響を与えることにつながります。
日本における活動
日本国内でもグローバル連携したオープンソースのコミュニティ活動は活発化しています。「CNCF Ambassador」(2025年8月現在、日本から8人)や、日本のローカルコミュニティである「Cloud Native Community Japan(CNCJ)」など、グローバルなコミュニティと地域との架け橋となる役割を担う人々も活躍しています。彼らはOSSプロジェクトのメンテナー、イベントの開催、登壇、翻訳、アップストリームトレーニング(メンターシップ)といった様々な活動を通して組織を超えたコミュニティ活動を行っています。
イベントの開催もさらに活発になっています。北米や欧州で開催されている「KubeCon+CloudNativeCon」はグローバルで最大規模のオープンソースカンファレンスの1つであり、1万人規模の開発者や企業が集う場となっています。CNCJの尽力により2025年に日本誘致が実現し、参加チケットが売り切れるほどの活況となりました。来年、2026年は開場を拡大して横浜で開催される予定になっています。
KubeCon+CloudNativeConが日本に誘致されたことは、日本のOSSコミュニティにとって画期的な出来事です。国内の知見を世界に発信し、同時に世界の知見を国内に取り入れる双方向の交流が強化されることになり、日本のオープンソース活動の存在感をさらに高めると期待されています。GitHubによる国別コントリビューター数ランキングの予想や実績のレポートを見ると、日本のコントリビューターが増加してランクを上げていく様子が伺え、日本のオープンソース活動はますます活性化していくことも予想されています。
このようなグローバルなイベントから得られる知見や人脈は大きな資産となります。国内の活動がグローバルコミュニティと直結していく様子を直に見ることができ、同時にそこに参加する機会を身近にすることが期待できます。国内で得られる知見を世界に還元し、また世界の動きを日本に取り入れることで、オープンソース活動をさらに強固なものにしていく貴重な機会となるでしょう。また、組織としてはこうしたイベントにスポンサーとして参加することもプレゼンスやブランド価値の向上、マーケティング、採用活動に大変有効です。
組織内や国内にとどまらず、グローバルに接続されたOSSコミュニティの一員として活動することこそが、オープンソース活動を真に価値あるものにし、エコシステムとともに自らも成長させることに繋がります。
まとめ
オープンソース活動は「OSSを使うだけ」ではありません。自ら改善や課題解決に乗り出すことで技術者や事業としての目的を果たし、その過程をグローバルなオープンイノベーションの場で進めることで社会貢献にも繋がります。それらを通じて世界中の技術者やエコシステム全体とともに成長することにより、技術力や評価を獲得することでしょう。そこに飛び込む勇気や投資は多少必要ですが、多くの価値に繋がっていきます。これらは個人と組織の両方に通じる観点です。個人・組織・エコシステム全体の三方良しとなる活動を進めていきましょう!次回は「Kubernetesコントリビューション入門(ハンズオン)」と題してお送りする予定です。お楽しみに!
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- LFがオープンソースにおけるDE&I(多様性・公正性・包摂)に関する調査レポートを公開、ほか
- Cloud Native Community Japanキックオフミートアップ レポート
- OpenSSFを拡大・支援するため1,000万ドルの新規投資を調達、「The 2021 Open Source Jobs Report」を公開、ほか
- Kustomizeのリードに昇格したエンジニアが語るOSSへの参加を持続させるコツとは
- SigstoreコミュニティがGAを発表、OSSのベストプラクティスを学べる新トレーニング「オープンソース管理と戦略」日本語版をリリース
- 「Open Source Forum 2019」開催 ― キーマンが語る企業や社会の要素となるOSS技術とは
- Keycloakの最前線を体感できるイベント「Keyconf 23」レポート
- LinuxCon ChinaでMicrosoftのエンジニアが説くオープンソースプロジェクト成功のポイントとは?
- 日立のOSSコントリビュータに訊いた組織のあり方と失敗談
- Red Hat、オープンソースPaaS「OpenShift」のコミュニティを設立