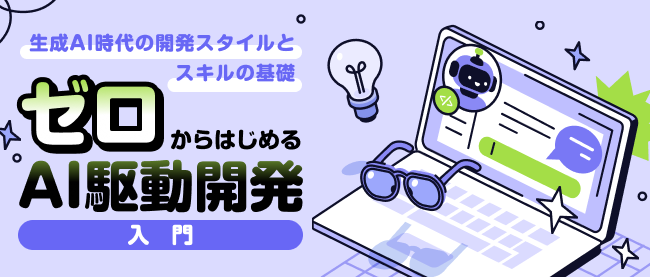PMOは4種類ある!それぞれの違いや導入メリットとは?

はじめに
これまで 基礎編、 知識編、 事例・実践編と3つの連載を通して、PMO(Project Management Office)という職種についていろいろな角度から紹介してきました。
PM(Project Manager)の補佐的な役割としてプロジェクト全体を把握し、適切な進捗管理や業務を効率化するための仕組みづくりなどを行う。さらには社内のチームや部署、クライアント企業など垣根を超えて横断的に動き、コミュニケーションを円滑にする。そうした活動を通して、プロジェクトを成功に導くことが、PMOの主な仕事です。
テクノロジーの進化、顧客ニーズの多様化、激しく変化する市場、加速するグローバル化……さまざまな背景からプロジェクトの複雑化が止まりません。
複数の企業や多くのメンバーが関わる大規模プロジェクトも、珍しいものではなくなりました。その中で、負荷が増えたPMの業務の一部を引き取り、広い視野でプロジェクトを捉えて最適化できるPMOの重要性はますます高まり続けているのです。
一方で、多様な関係者や管理業務で複雑化しているのはプロジェクトだけに限りません。例えば、複数のプロジェクトをとりまとめる各事業部の運営、そして企業全体の組織運営にも同じことが言えますよね。
実は、そのような領域で活躍するPMOも存在しているのです。
前回までの連載で主に紹介してきたPMOは「プロジェクト内PMO」と呼ばれるPMOですが、PMOは大きく分けて以下の4種類に分類されます。
- プロジェクト内PMO
- 部門PMO
- コーポレートPMO
- 第三者評価PMO
私自身、すべてのPMOを経験してきましたが、どのタイプのPMOも今後さらに幅広い業界から求められていくだろうと感じています。
これからスタートする新連載では、これら4つのPMOについて深掘りして紹介していきます。どのような領域でどのような役割を担うPMOなのか、またどのようなスキルや知識が求められるのか。実際の事例を踏まえながらわかりやすく紹介したいと考えています。
今後、PMOを目指したいと考えている方、PMOの導入を検討している企業の方にも参考にしていただける内容をお届けしたいと思います。ぜひご期待いただけたら嬉しいです。
4つのPMOの違い
4種類のPMOの詳しい説明は今後の連載記事にて紹介しますが、今回はまず、4種類の違いをご理解いただくために、それぞれの特徴を簡単に解説したいと思います。
・プロジェクト内PMO
事業部内の特定のプロジェクト単位で配置され、PM支援、プロジェクト全体の管理、推進を担います。
・部門PMO
特定の事業部門に配置され、部門内の管理、他部門との連携、複数のプロジェクトの横断的な支援で相乗効果を促進するなど、部門全体の成長戦略を支えます。
・コーポレートPMO
経営層直下に配属され、全社レベルでさまざまなプロジェクトの進行を管理するほか、部門間の連携支援や標準化、ガバナンス強化などにも携わり、企業全体のマネジメント、経営判断をサポートします。
・第三者評価PMO
多くの場合、社外から派遣され、事業部や経営層、プロジェクトから完全に独立したポジションとして配属されます。第三者的目線で会社やプロジェクト運営のモニタリング、評価を担います。
このように、4つのPMOは配属される場所や担う業務も異なります。
さらに事業会社側のPMOなのか、ベンダー側のPMOなのかによっても役割に違いがありますので、実質的には「8つに分類される」とも捉えられるのです。
PMOの導入で期待できることとは?
紹介した4種類のうち、「プロジェクト内PMO」以外の3つ「部門PMO」「コーポレートPMO」「第三者評価PMO」はまだ一般的にあまり認知されていないため、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際は「○○PMO」と名前がついていないだけで、多くの企業においてほぼ同等の業務を行っている人、部署は存在しているはずなのです。
下図は、各PMOのポジションを可視化したものです。例えば、コーポレートPMOの仕事は経営企画部、第三者評価PMOの仕事は内部監査部やリスク管理部などが、その役目を担っている企業も多いのではないでしょうか?

【出典】甲州潤 著『DX時代の最強PMOになる方法』
そうなると「すでに似たような部署があるのに、あえてPMOを設置する必要があるのか?」という疑問が生じるかもしれません。確かに、企業によってはすでにPMO的な人材が部署内にいる場合もあるでしょう。その際は、PMOの必要性を感じないかもしれません。
では、そうした人材がいない場合、PMOを配置するメリットとは何なのか。
私は「事業推進力の強化」だと考えています。
企業により異なるとは思いますが、例えば、経営企画部は経営陣の意見を汲み取りながら、経営戦略の立案や実行のための情報収集や市場調査、事業や労務状況の確認、管理などを行う位置付けであるのが一般的です。
一方、同じように経営層直下に配属されている「コーポレートPMO」の場合、そこからもう一歩踏み込みます。ただ情報を集めて管理するだけでなく、「事業をさらに前進させて計画通りに理想的なゴールにたどり着くにはどうしたらよいか」を念頭に置き、広い視野で考え、行動する「実行部隊」としても機能するのです。
ときには必要に応じて経営陣に対し、「この社内規則は業務の進行を妨げているので、廃止か見直しをした方がよいのでは?」「この経営方針は現場と合っていないのではないか?」といったような改善提案を行うこともあります。
もちろんこのような場では、感情的に「物申す」のではなく、根拠やデータに基づき、わかりやすく情報を整理して伝えることが求められます。ここにPMOの「ファシリテーション力」や「論理構成力」といったスキルが生かされるのです。
他のPMOにおいても同様です。部門PMOであれば、複数プロジェクトの進行管理だけでなく、「この部門とこの部門が連携すればパフォーマンスを最大化できる」など連携によって引き出される相乗効果を検討することもあります。
第三者PMOなら、プロジェクトの脱線や暴走を防ぐための改善策、あるいは透明性をより高めるための仕組みの提案など、客観的かつ冷静な目線で組織にフィードバックを返す役割を果たします。
社内の1部署だけでは、どうしても部署内の仕事だけに注力しがちです。しかし、企業活動は単体で完結する業務ばかりではありません。常にいくつものプロジェクトや部門、事業が走っているわけです。
組織全体の利益を考えれば、それらを俯瞰しながら、それぞれの関係性を把握し、全体最適を見据えて横断的に業務の標準化や効率化を考え、動ける存在が重要であり、そこで力を発揮できるのがPMOなのです。
経営企画部や監査室がすでにあっても、PMOが加わることで事業推進力が高まり、組織の成長をさらに加速させることができるのです。
最近では、まず外部PMOを導入してプロジェクトや事業を軌道に乗せつつ、社内でPMO人材を育成していくという企業も増えています。PMOへの理解とニーズは、確実に広がっていると感じる日々です。
おわりに
今回は新連載に先立ち、4つのPMOの違いや、導入によって期待できることなどをお伝えしました。
今後は4種類について、より詳しく解説していくため、事業会社側とベンダー側に分けて連載を進めていきます。
実際に現場で起こった事例などもご紹介しながら、そのPMOがどんな立ち位置で、成果を出すためにどんなスキルが必要なのかなど、リアルなPMOの姿をお伝えしていきます。
次回は、「事業会社に所属するプロジェクト内PMO」を掘り下げていく予定です。 どうぞお楽しみに!