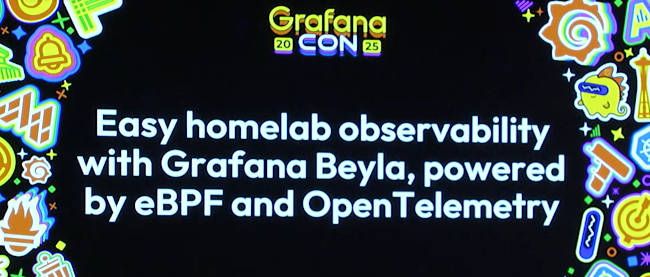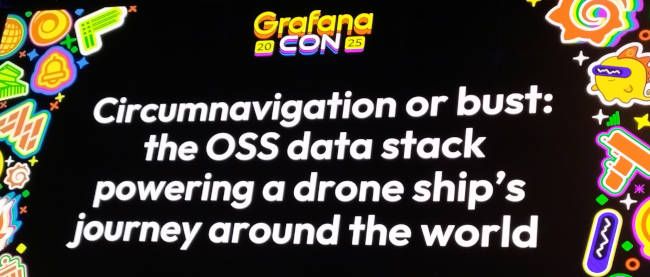GrafanaCON 2025、Grafana Labsのキーパーソンにインタビューを実施(前半)

GrafanaCON 2025はオープンソースであるLGTMスタック※に関するテクニカルカンファレンスだが、実質はGrafana Labsのエンジニアが技術的な解説を行い、ユーザーがユースケースを語るというものだった。今回はそのGrafana Labsのキーパーソンにインタビューを行い、多面的に「Grafanaの中の人」の想いを解き明かしていこうという稿である。
※ LGTMスタック:ログ管理のLoki、ダッシュボート/可視化のGrafana、トレースのTempo、そしてメトリクスのMimirを総称したもの。
インタビューを行ったのは、共同創業者のTorkel Ödegaard氏、CTOのTom Wilkie氏、そしてDeveloper Program DirectorのTed Young氏の3名だ。この稿では前半としてTorkel Ödegaard氏、CTOのTom Wilkie氏のインタビューを紹介する。
共同創業者のTorkel Ödegaard氏に訊く、ユニークなユースケースが登場する理由
最初はTorkel Ödegaard氏のインタビューだ。
自己紹介をお願いします。
Ödegaard:私はもともとデベロッパーでC#のプログラムを書いており、その頃はWebのバックエンドなどを担当していました。当時からモニタリングというシステムはありましたが、私が使いたくなるようなモノではなく、これを何とかしたいと思って仲間と始めたのがGrafanaの最初だったと思います。
今回のカンファレンスではユニークなユースケースが多くて印象的でした。あれは意図的に選んでいるんですか?
Ödegaard:GrafanaCONでは毎回かなりユニークなユースケースが紹介されます。私も毎回驚かされるくらいです(笑)。今回も月面着陸のプロジェクトや無人ボートで世界一周するプロジェクトなどがありましたが、一つには常時インターネット接続が行えるような状況ではないシステムにおけるオブザーバビリティをどうやって実装するのか? という部分にフォーカスしたという側面もありますね。
その部分は、高速なインターネット接続が要求されるSaaSベースのオブザーバビリティに対する回答でもあったわけですね。
Ödegaard:そう言っても良いかもしれません(笑)。
私はThe Linux Foundation(LF)やCloud Native Computing Foundation(CNCF)のさまざまなカンファレンスに参加していますが、そこで感じるのは、オープンソースだけではマネタイズが難しいエコシステムの中で彼らはトレーニングと試験制度を充実されることでエンジニアの底上げとマネタイズに行おうとしているという点です。Grafana Labsのオブザーバビリティスタックについてもそのような計画はありますか?
Ödegaard:過去にGrafana Universityというトレーニングのプログラムを実施したことがありましたが、現在では行っていません。LFやCNCFがトレーニングと試験を拡大しようとしていることは知っていますが、同様のことを小さな組織が運営するのは、現実には非常に難しいと思います。大きな要因はソフトウェアそのものの進化が速いことです。それに追従してトレーニングや試験を更新していくのは大きな労力が必要になるからです。なのでソフトウェアのドキュメントを充実させること、その上でそのソフトウェアに関するAIアシスタントを作ってデベロッパーの質問に答えられるようにするというのが現時点での良い選択肢だと思いますね。
あなたにとってのチャレンジはなんですか?
Ödegaard:常に良いユーザーエクスペリエンスを作ること、ですね。APIであれダッシュボードであれ、それを使うエンジニアが苦労せずに欲しいものを手に入れられるという状況を作るというのが私の仕事だと思っています。
Ödegaard氏の回答は常にデベロッパーの視点で何がどうあるべきか? を考えていることを思わせる内容で、主に運用者が使うツールとしてのオブザーバビリティからデベロッパーが主体的に使うツールとなるべきという発想だった。これは次にインタビューを行ったCTOのTom Wilkie氏にも通底する考えのようだ。
CTOのTom Wilkie氏に訊くGrafana LabsとAI
2025年2月にインタビューをして以来の再会となりました(以下、参照)。お元気でしたか?
●参考:Grafana Labs CTOのTom Wilkie氏インタビュー。スクラップアンドビルドから産まれた「トラブルシューティングの民主化」とは
Wilkie:相変わらずだね。君も元気そうで良かったよ。
先ほど、Torkel Ödegaard氏にインタビューを行いましたが、彼の視点が常にデベロッパー寄りというかオブザーバビリティをデベロッパーがやるべきという意識が強いことに驚きました。
Wilkie:そうかい?でもDevOpsは単に開発から運用までを同じサイクルで回すというだけではなく、デベロッパーが本番環境で自分が書いたコードがどんな仕事をしているのかを意識するべきだということにも通じていると思うね。そしてそれは業界のトレンドになっていると思う。個人的にはデベロッパーは単に機能を実装するだけではなくて本番環境についても責任を持ちたい、本番環境は別の人の責任だというのは違うんじゃないか? と感じていると思う。
組織には開発チーム(Dev)と運用チーム(Ops)が存在している。過去はそれでも良かったが、今やそれではビジネスが成り立たないという時代になったというだけのことだよ。すべての企業においてソフトウェアが重要なコアとなっている現在では、デベロッパーが重要な仕事を担っていることには変わりはない。
多くのオブザーバビリティベンダーが生成AIをサービスの中に取り込んで「根本原因の解明に使える」と宣伝していますが、Grafana Labsの差別化のポイントはなんですか?
Wilkie:我々はかなり早い段階からAI、マシンラーニングに取り組んできた。それは2月に君のインタビューで答えた通りだが、他社との違いを挙げるなら、Grafana Labsはオープンで透明であることを常に優先してきたということだろうね。OpenTelemetryへの対応もその一つだが、他社はどうしても独自のエージェント、ブラックボックスのロジックなどに向かいがちになる。AIに関して言えば他社は宣伝が上手いとは言えるんじゃないかな。我々は上手くないというか宣伝はしていないからね(笑)。
前にも答えた通り、非構造化データを使ってLLMを作ることには失敗したのでやり直した。そういう部分もこうやってオープンに話している(笑)。もう一つ言えば、我々は毎日、本番環境のリアルなデータを使ってAIをリファインしている。それは研究開発のための実験室ではなく本番で使わないとAIを良いものにできないからという想いがあるからだ。
もう一つ、AIについて良い成果があるとすれば、私のようにかつてはエンジニアで今や現場を離れている人間が「今のシステムはどうなっている? 何が問題なんだ?」と質問をして部下を困らせることがなくなることだね。AIに質問をして回答を作らせることで、部下の時間を無駄にしないという利点があるんだよ。
AIには関係しないがオープンであることの利点をもう一つ付け加えたい。オープンではない独自のオブザーバビリティを開発している企業は、自社の開発リソースだけで集めたデータを保持して処理する必要がある。一方オープンなソフトウェアであれば、さまざまな企業が協力してデータを集め、そこからの知見を応用できる。そしてその結果をさらに公開することでエコシステム全体の価値が高まる。自社だけでやろうとすればコストが高くなって結果として価格に跳ね返るのは当然だろう。
最後のAIを使うことで部下の時間を無駄にしないという回答は、いかにもロンドン育ちのジョークとも言える内容だった。Wilkie氏の回答を「ですます」調にしなかったのは「ですます」調ではWilkie氏のトークのニュアンスが伝わらないと思ったからだが、伝わっただろうか。両氏ともデベロッパーがオブザーバビリティの主体になるべきだと言う点と生成AIも含めてオープンであることの重要性を力説した内容となった。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- GrafanaCON 2025開催、最新のGrafana関連の情報を解説。キーノートから見るリアルな運用現場に対応したAIアシスタントとは?
- Grafana Labs CTOのTom Wilkie氏インタビュー。スクラップアンドビルドから産まれた「トラブルシューティングの民主化」とは
- GrafanaCON 2025、太陽光発電による完全自走式ボートで世界一周を目指すプロジェクトのオブザーバビリティを紹介
- GrafanaCON 2025、インストルメンテーションツールのBeylaを解説するセッションを紹介
- GrafanaCON 2025から、スキポール空港のキオスク端末のオブザーバビリティを解説したセッションを紹介
- オブザーバビリティのNew Relicが発表した新機能についてCTOに詳細を訊く
- KubeCon Europe 2025、DynatraceのDevRelにインタビュー。F1でも使われているオブザーバビリティとは?
- Observability Conference 2022、日本ユニシスのエンジニアが解説するデベロッパーにとってのオブザーバビリティ
- Observability Conference 2022から、サイボウズのオブザーバービリティ事例を紹介
- Microsoftがリードするモダンな分散システム用ランタイムDaprとは?