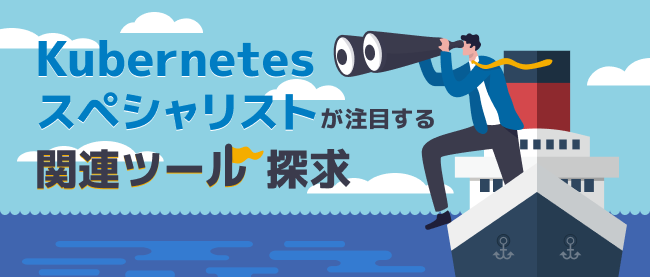毎朝Slackで送る「社員たちへの手紙」。続ける理由は、その先にある「人を動かすシステム」づくり

- 1 3年半にわたって毎朝1088回、書き続けている「社員たちへの手紙」
- 2 書くことは苦手だったが、続けるうちにだんだん面白くなってきた
- 3 500回続けて分かった、新しい視点を生む「掛け算」の書き方
- 4 誰かを思い浮かべて書く。「手紙」は読み手の社員との見えない対話
- 5 ネタ帳なしで続ける秘訣~面白さは日常のいたる所にころがっている
- 6 毎朝の「手紙」を通じて、「一人ひとりの行動を変える」のが自分の務め
- 7 「手紙」のもう1つのねらいは、「発信する文化を社内に根付かせる」
- 8 「継続は力なり」~続けることで書き手にも読み手にも変化が起きた
- 9 「書く」経験を通して、エンジニアとしての成長にチャレンジしよう
今の時代、若手エンジニアが勉強したいと思えば、いくらでも教材や資料はインターネットで手に入る。だがそんな便利な時代であっても、やはり先輩たちの生きた経験に裏打ちされたアドバイスは貴重だ。本連載では、情報インフラ系SIerとしての実績の一方で、現場で活躍できるエンジニア育成を目指した独自の技術研修「BFT道場」を展開。若手技術者の育成に取り組む、株式会社BFT 代表取締役 小林道寛氏に、ご自身の経験に基づくスキルアップのヒントや、エンジニアに大切な考え方などを語っていただく。
3年半にわたって毎朝1088回、
書き続けている「社員たちへの手紙」
皆さん、こんにちは。株式会社BFTの小林道寛です。
実は、私は毎日、簡単な文章~「社員たちへの手紙」とでも呼びましょうか~を、社内のSlackに書いて、社員の皆さんに読んでもらっています。すでに3年半続けて、回数もすでに1,000回を超え、つい先日確認したら1,088回に達していました。
「ええっ、毎日社長の訓話を読まされるの!?」と思う方も、いるかもしれません。でも、ご安心ください。「もっと売り上げを上げろ」とか「技術者たるものの心得は!」みたいなことは、私自身とても苦手です。では、なぜそんな私が、何年も社員のみんなにメッセージを送り続けているのか。今回はそのきっかけや「手紙」に込めている私の思いなどを、少しお話ししたいと思います。
書くことは苦手だったが、
続けるうちにだんだん面白くなってきた
正直に言うと、私はもともと文章を書くのは下手だし、嫌いでした。しかしSEの仕事をしていると、設計書を書いたり提案書を書いたりと、業務の中でどうしても文章を書かなくてはいけません。そこで「お客様からお金をいただく以上は、きちんとした設計書を書かないといけない」と思ったのが、就職して間もない私が、初めて「文章を書く」というのを意識したきっかけでした。
もちろん、決心したところで最初は全然書けません。当時はあるテレビ局のシステム子会社にいたのですが(第1回参照)、そこはヘッドハンティングされてきたベテランの技術者も多くて、そういう方たちに添削をお願いしたのです。彼らも、忙しい中で私のつたない文章を熱心に読んでは直してくださって、今でも本当に感謝しています。そういう先輩方のご指導もあって、だんだん面白さも感じるようになり、書くことが好きになっていきました。
そんな私が本格的に「書く」ことを始めたのは、10年以上前、当社で新卒採用を担当していた頃でした。あるとき、大手量販店の人事担当者の書いたブログが評判を呼び、大勢の人に見てもらえたという話を聞いたのです。そこから「じゃあ、ひとつ当社もブログを書くか」ということになって、私が過去に経験した「エンジニアってこんなもんだよね」みたいな話を書き始めました。
実は、そのときも、そもそもブログなんて興味なかったし、書けるとも思っていませんでした。それでも、ほぼ毎日ぐらいのペースで書いていくうちに「意外に面白いじゃないか」と思うようになりました。苦手なりに書いていると、数をこなして上手くなる部分があったりして、自分でも「なんかスムーズに書けるようになってきたな」と感じたものです。
次に文章を書く機会が巡ってきたのはつい最近、あるHRMツールを社内に導入したときです。「このツールのお知らせ機能を使って、前にやっていたブログみたいなのを書いてもらえますか?」と担当者に頼まれました。そう言われて「ま、書いてみるか」と思ったのが現在、毎朝Slackに書いている「社員たちへの手紙」の始まりです。
500回続けて分かった、
新しい視点を生む「掛け算」の書き方
毎日600~800文字程度の文章を書いていると、だんだんと自分なりのスタイルが見えてきます。最初の頃は400文字ぐらいと短かったのですが、最近は慣れてきて少し長くなりました。
500回ぐらい書いた後に気づいたのが「掛け算」の書き方です。1つのテーマだけで書こうとすると、よほど深い内容にしなくてはいけないので、実は書きにくいのです 。そこで、あるテーマに別の視点を掛け合わせることで、新しい発見や面白さが生まれることに気づきました。
例えば「昨日、マーケティングを教えてくださった方にお会いしました」という話を書きつつ、日本で広まっている「THE MODEL」というマーケティング手法の話を掛け合わせる。
具体的には「THE MODELというのはアメリカで生まれたのだけど、日本で広まったのはある人がアメリカのベンダーに入って学び、帰国後いろんな会社に転職しながら広めたから」「実は、いま当社にいるTHE MODELに詳しい社員も前職で学んだのだけど、その前の会社がまさにそのエバンジェリストを参考にした」みたいなウラ話を披露しつつ、「あの話題のマーケティング手法って、こんなふうに広まっているんだよね」みたいな「ちょっと興味をひく話」に仕上げるのです。
こうした「掛け算」の発想で書くことで、読む人も「あ、そこに行くんだ」「話が大きいな」と楽しんでもらえるようになりました。
誰かを思い浮かべて書く。
「手紙」は読み手の社員との見えない対話
「社員たちへの手紙」で文章を書くとき、私は必ず誰かを頭に浮かべています。例えば「人事の彼女に、こういう話を伝えたいな」といった具合に、誰に何を伝えるかを頭の中で具体的に思い描くのです。
すると、面白いことに読んだ相手から「あれ、私に伝えようとしたんでしょう」などと言われて、「あ、気づいた?」みたいなやりとりになることもあります。必ず特定の誰かを想定するわけではありませんが、多くの場合は「これは誰々に」とか「昨日話していたあの話、すごく良かったから書き留めておこう」という感じで必ず起点には人がいて、そこから始まります。
また、そうやって書き残すことの大切さも感じています。その場その場で話して「これってこうだよね」などと話すこともありますが、書き残しておいて後から読み返すと「あ、私はこのときこんなことを言ったな」「そう、そうだよね」と思い返すことができる。人間の記憶には限界があって、新しいことを覚えると古いことは忘れてしまいがちです。でも、書き残しておけば、必要なときに思い出すことができるのです。
ネタ帳なしで続ける秘訣
~面白さは日常のいたる所にころがっている
毎朝書くとなると「ネタはどうしているの?」とよく聞かれます。実は私は、いわゆる「ネタ帳」的なものは一切持っていません。最初の頃は「こんなこと書けそうだな」というものをリストにしたこともありましたが、そのうち「別に、こんなものなくてもいいな」と思うようになりました。
私は、家から会社まで40分ぐらい歩いて通勤していますが、「さて、何を書くかな」と思いながら歩き、会社にたどり着いて「うーん、決まらない。どうしよう…」という日も正直あります。そういうときは、昨日や今週、先週の話の中で、何を面白いと思ったかを思い出します。そうやって思い出していくと、結構何かしら出てくるものなのです。
通勤の日常の中にも、面白いことがたくさん見つかります。先日は、満員電車で学生がスマートフォンを使って勉強している。たまたま画面が見えたら、難しい英単語の意味を次々と正解していて「この子、頭が良いんだ」と驚いたり。一方で、いまだに赤い透明シートを使って暗記している子もいて「勉強方法って人それぞれなんだな」と感心したりしました。
あるいは、私が行く立ち食いそば屋には欧米人の女性店員さんがいるのですが、店主がその人にすごく無遠慮なことを言うんですよ。たぶん店主は、ずばずば物を言い合える関係が大事だと思ってやっているのでしょう。でも、お姉さんは「はあ?」みたいな感じで「絶対分かってないよ」「通じてないよ」と思いながら横で見ています。
こうした日常の小さな発見を面白がる視点があれば、ネタに困ることはありません。むしろ、思っている以上にいっぱいあって「驚くなあ」と思うぐらいです。
毎朝の「手紙」を通じて、
「一人ひとりの行動を変える」のが自分の務め
さて、なぜ私が「社員たちへの手紙」をこれほど長く続けているのか、そろそろ本質的な理由をお話ししましょう。
全社会議を年に4回ぐらいやっても、自分の話せる時間ワクはせいぜい30分ぐらいです。ということは、1年間でわずか2時間ぐらいしか私の話を聞く機会のない社員もかなりの割合でいるわけです。それで伝わるか伝わらないかと言うと「そんなもの、伝わるわけないだろう」と言われちゃいますよね。
だからこそ、私としては毎日少しずつでも「うちの社長は、こんなことを考えているんだな」とか「こういう物の見方をしているんだな」ということを、みんなに知ってもらいたい。もちろん、読み手が賛成できる内容ばかりではなく、反対される内容もあったりします。毎日毎日、暑苦しい話を書いていると読む方も辛いから、立ち食いそば屋の話を入れてみたりして、変化をつけることも意識しています。
さらに重要なのは、これが単なる「トップメッセージ」ではないということです。私は、システムを作るときもそうなのですが、人の働き方を変えるというか、人の行動を変えることがテーマとしていつも強く意識の中にあるのです。
「社員たちへの手紙」は毎日決まった時間にSlackに投稿しているので、それを見ることが社員一人ひとりの「働く習慣」になる。通勤や客先に向かう電車の中で「よく分からない社長の小話でも、まずは読むか」程度の軽い気持ちで良い。それが、その人の朝のルーティンになってくれたら、人の働き方を変えるとか、働くリズムを作ることにもつながるかもしれない。そのために小さな努力を続けるのが、私の経営者としての仕事だと思っています。
「手紙」のもう1つのねらいは、
「発信する文化を社内に根付かせる」
実は、この「手紙」には、もう1つ大きな目的があります。それは「発信する文化」を会社に根付かせることです。
正直なところ、以前は自分たちの会社はBtoBなので、それほど外部に発信する必要性はどないと思っていた時期もありました。安定的にお客さんを確保できていれば、自分たちのことを知ってもらう必要性って、それほど重要じゃないのかなと。
でも、それは違うなと気づきました。自分たちがこういうケイパビリティを持っていて、こういうことに取り組んでいるというのを知ってもらうことで、より面白い機会が増えてくるし、取引先も増えていきます。「受信するよりも発信する、働きかけていくことを、もっと大事にしていった方が良い」と悟ったのです。
実際、私が毎日書き続けることで、社内にも少しずつ変化が生まれてきています。同じように、Slackで自分から発信している人も増えてきました。「こんなことに疑問を持ったんだよね」とか「これ、ちょっと悲しかったんだ」とか、SNS的な呟きのようなものを書く人もいます。そうやって何を自分が考えているのかを他者に働きかけて伝えること自体は、すごく良いことだと思っています。
「継続は力なり」
~続けることで書き手にも読み手にも変化が起きた
1,000回を超えて続けてきて、自分自身にもさまざまな変化がありました。一番大きいのは、性格が少しポジティブになったことです。
最近「ジョブ・クラフティング」という言葉が流行っています。これは、仕事の内容や働き方に改めて向き合い「これって、自分にとってどういう意味があるんだ?」と自分自身で主体的に再定義することです。起きた事象に対して、それを再度解釈し直すことでもあります。
例えば、何かイヤなことがあったときも、その瞬間は「どういうことだよ」「なんだこりゃ」と思って終わりです。でも、それを文章に書こうとすると、もう一度そのできごとを見つめ直すことになる。すると「ああ、そういう視点もあるのか」「これって、そういう受け止め方にあるのね」と、少し違った見方ができるようになります。
そうやって改めて考えてみると、実はネガティブに捉える必要はないことだなと思えたり、むしろ学びになったと感じられたりもする。ジョブ・クラフティングとは、イヤなことを「イヤだった」で終わらせず、自分の中で見直して分析して昇華させる、いわば自分と自分の経験を大切にする営みだと言えるでしょう。
もちろん、私だけではなく読む側にも変化が生まれています。この間、新卒の子が「研修が早く終わって時間ができたから、昔の『手紙』を読み返していたんですよね」と言ってくれました。「もう○月ぐらいまで読みましたよ」なんて言われて「そんなに読んでくれたんだ」と嬉しくなりました。自分の頑張りを一番読んで欲しい人からほめてもらえた気分です。
また「読んでますよ」と声をかけてもらうと、お互いにそれを経由して少し人に対する理解というか、双方向の理解みたいなものが広がっていく、深まっていく部分もあります。社内向けのメディアだからこそできる、そんなつながりの広がりを感じています。
「書く」経験を通して、
エンジニアとしての成長にチャレンジしよう
最後に、今回のテーマに関して、若手エンジニアの皆さんにぜひ伝えたいことがあります。それは、技術者にとって「書く」ことは、単なるドキュメント作成以上の価値があるということです。
私自身、設計書を書くために文章の練習を始めましたが、そこから得たものは技術文書を書く能力だけではありませんでした。頭の中で立体的に物事を組み立てる力、相手に伝わりやすい構造を考える力、そして何より、自分の考えを整理し、深める力を身につけることができました。
1,000回を超えてもなお続けているのは、書くことが楽しいからです。具体的には、いろいろなものごとに対して少しずつ解釈が深まっていくこと、読んでいる人とのつながりがそこに広がっていくことなど、いくつも面白いなと思うことが、書くことから生まれてきます。
皆さんも、技術ブログでも社内の情報共有でもいいから、何か書き始めてみてはどうでしょうか。最初はつらいかもしれません。でも続けていくうちに、きっと自分なりのスタイルが見つかり、書くことの楽しさや価値を発見できるはずです。そして、それは必ずエンジニアとしての成長にもつながっていくと、私は自分の「手紙」の経験をもとにお約束します。
さて、次回はどんなテーマを取り上げましょうか。よろしければ、どうぞ引き続きお付き合いください。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- 休日は自分の部屋で引きこもるのも良し。「オン-オフをはっきり分けてストレスをつくらない」
- そのグラフや資料、本当に伝わってる?「資料作成スキル」を磨くための特訓法
- エンジニアのビジネススキルは、いわば「オプション」自分の「やってみたい」と思うところを自由に選ぼう
- 「バリバリのエンジニア志向」だった私が、気がついたら「企業経営者」になっていた理由
- 先行き不透明な時代だからこそ、ときには立ち止まって「自分の現在と未来」を考えてみよう
- KubeConで富士通のエキスパート江藤氏に訊いたOSSの勘所
- 他業種の人たちと働く経験を通じて、自分のエンジニアとしての「引き出し」を増やそう
- キャリアのスタート台に立ったら、まず仕事に取り組むための「マインド」をかためる
- 雑談(会話)のネタがない時
- 「個人の成果を正しく評価」して意欲を高め、「突き抜けた存在感を持つエンジニア」に育てたい