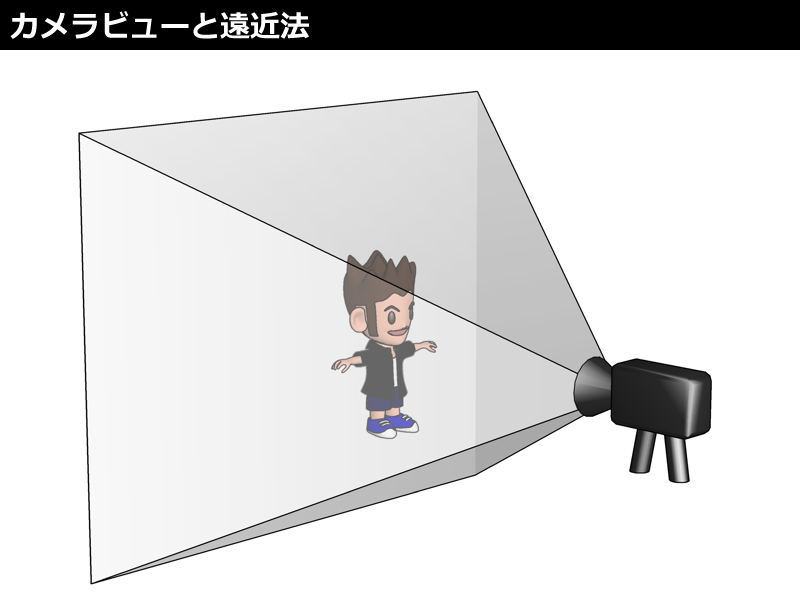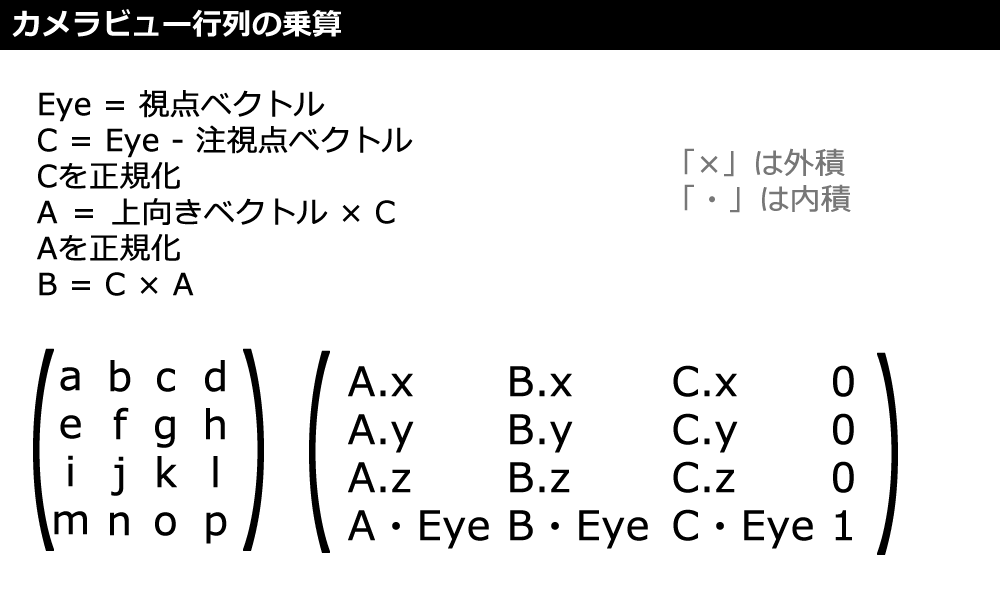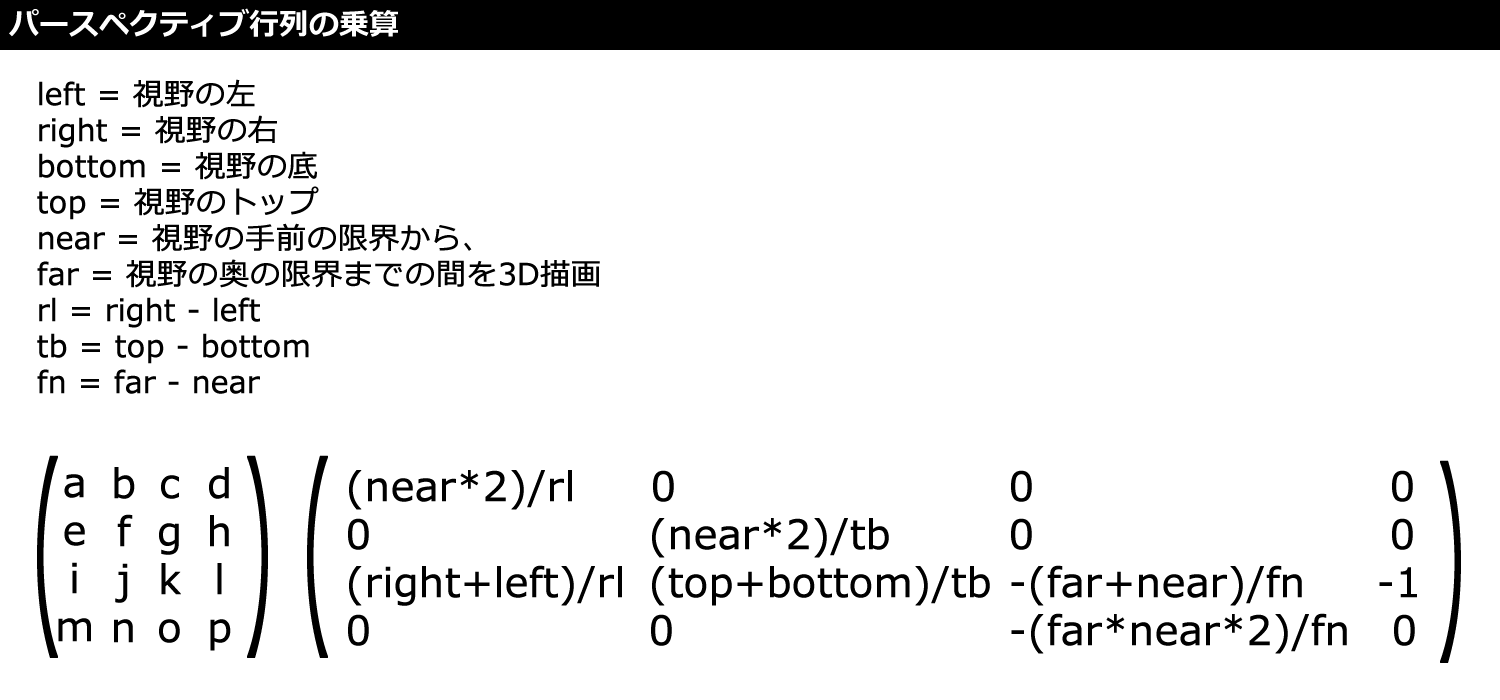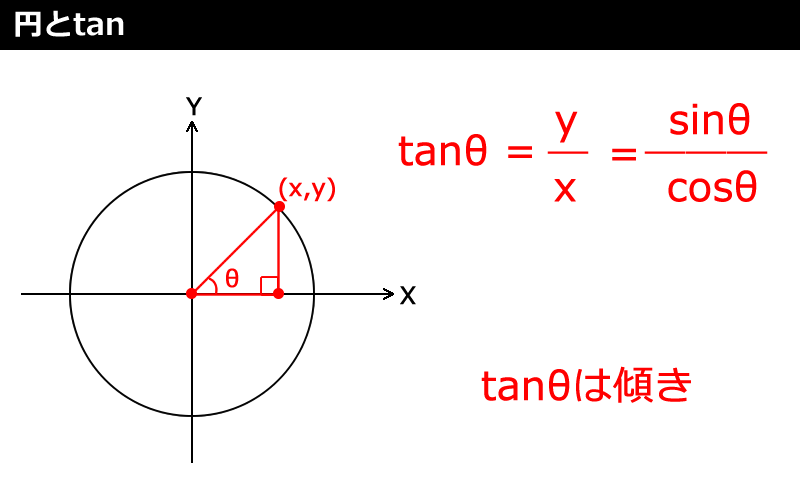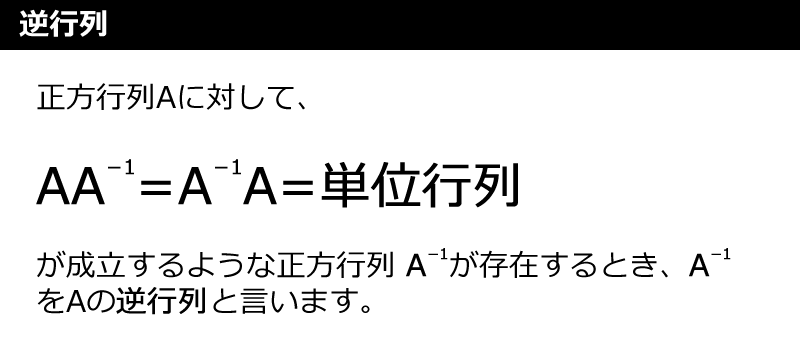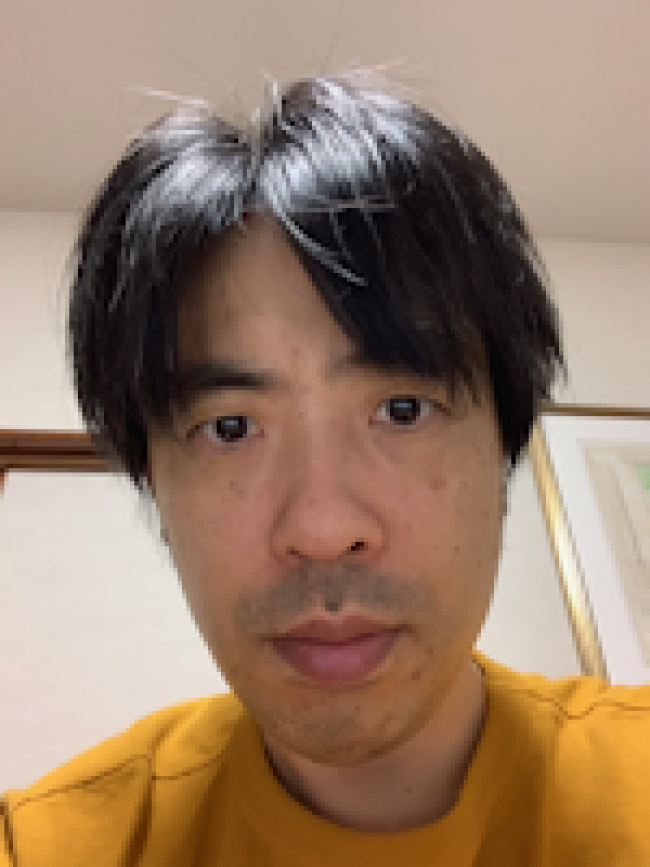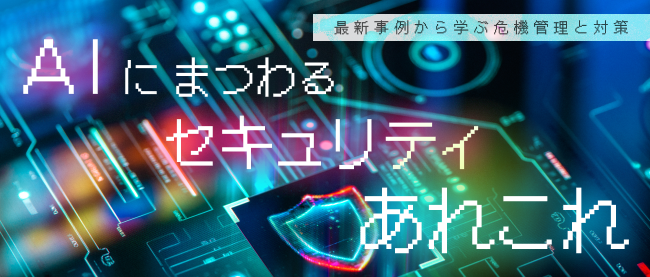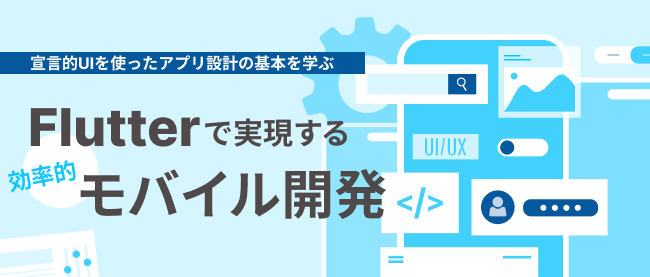3Dの移動や回転、拡大・縮小する「行列」について学ぼう

ビューとパースペクティブ
「ビュー」はカメラの「視点」と「注視点」と「上向きベクトル」を元に、カメラを3Dモデルなどに向ける行列です。カメラ視点はカメラの目の位置、カメラ注視点はカメラがどの座標に向いているか、上向きベクトルはカメラ自体の傾きです。
「パースペクティブ」は遠近法をかける行列です。これで3Dモデルがより立体的によりリアルな大きさで表示できます。一般的に3Dプログラミングでは、まず頂点に移動行列(平行移動、回転、スケーリング)、次にビュー行列、最後にプロジェクション行列(ここではパースペクティブ行列)を乗算します(図10)。
カメラビュー行列
カメラの視点から注視点の方を向けるには、図11のようにビュー行列を乗算します。一見カメラが向いているように思われますが、モデル全てを移動させてカメラが向いているように見せています。これも行列同士を乗算して計算します。
・サンプルコード「lib」→「Matrix3D.js」 lookAt(eye, at, up) {
var z2 = eye.subtract(at);
z2.normalize();
var x2 = up.crossProduct(z2);
x2.normalize();
var y2 = z2.crossProduct(x2);
this.e[ 0] = x2.x;
this.e[ 1] = y2.x;
this.e[ 2] = z2.x;
this.e[ 3] = 0;
this.e[ 4] = x2.y;
this.e[ 5] = y2.y;
this.e[ 6] = z2.y;
this.e[ 7] = 0;
this.e[ 8] = x2.z;
this.e[ 9] = y2.z;
this.e[10] = z2.z;
this.e[11] = 0;
this.e[12] = -x2.dotProduct(eye);
this.e[13] = -y2.dotProduct(eye);
this.e[14] = -z2.dotProduct(eye);
this.e[15] = 1;
}
透視投影変換行列
「透視投影」とは、近くのものは大きく、遠くのものは小さく見せる遠近法をかける計算です。よく「パースをかける」と言いますが、これは「Perspective(パースペクティブ、遠近法)」から来ています。図12のように透視投影変換行列を乗算します。これも行列同士を乗算して計算します。
図12の「top」「bottom」「right」「left」は、次のサンプルコードのように計算します。「fov」引数は「視野角」、「aspect」引数は「アスペクト比(縦横比)」を「near(近く)」~「far(遠く)」の間まで3D描画します。基本的なことですが、図13のように「Math.tan(ラジアン)」の「タンジェント」についても解説します。
・サンプルコード「lib」→「Matrix3D.js」 perspective(fov, aspect, near, far) {
let top = near * Math.tan(fov * Math.PI / 360.0);
let bottom = -top;
let right = top * aspect;
let left = -right;
let rl = (right - left);
let tb = (top - bottom);
let fn = (far - near);
this.e[ 0] = (near * 2) / rl;
this.e[ 1] = 0;
this.e[ 2] = 0;
this.e[ 3] = 0;
this.e[ 4] = 0;
this.e[ 5] = (near * 2) / tb;
this.e[ 6] = 0;
this.e[ 7] = 0;
this.e[ 8] = (right + left) / rl;
this.e[ 9] = (top + bottom) / tb;
this.e[10] = -(far + near) / fn;
this.e[11] = -1;
this.e[12] = 0;
this.e[13] = 0;
this.e[14] = -(far * near * 2) / fn;
this.e[15] = 0;
}
【サンプルコードの解説】
top変数は「near * Math.tan(fov * Math.PI / 360.0)」と計算します。
bottom変数はtop変数のマイナスです。
right変数はtop変数をアスペクト比から求められます。
left変数はright変数のマイナスです。
その他の行列計算
その他にも最低限知っておくべき行列計算として「逆行列(インバース)」と「転置(トランスポーズ)」があります。
逆行列
「逆行列」は図14のような行列式が成り立つ行列のことです。ある行列に逆行列を乗算すると単位行列になります。「inverse」は「逆数」「逆の」を意味する英語です。計算方法は次のサンプルコードの通りです。
ここで、inverseメソッドに「static」が付いていますが、スタティックメソッドはインスタンスを生成しなくても、ここでは「Matrix3D.inverse(引数)」のように「クラス名.メソッド名()」で呼び出せるメソッドのことです。
・サンプルコード「lib」→「Matrix3D.js」 static inverse(mat) {
var matrix = new Matrix3D();
var a = mat.e[0], b = mat.e[1], c = mat.e[2], d = mat.e[3],
e = mat.e[4], f = mat.e[5], g = mat.e[6], h = mat.e[7],
i = mat.e[8], j = mat.e[9], k = mat.e[10], l = mat.e[11],
m = mat.e[12], n = mat.e[13], o = mat.e[14], p = mat.e[15],
q = a * f - b * e, r = a * g - c * e,
s = a * h - d * e, t = b * g - c * f,
u = b * h - d * f, v = c * h - d * g,
w = i * n - j * m, x = i * o - k * m,
y = i * p - l * m, z = j * o - k * n,
A = j * p - l * n, B = k * p - l * o,
ivd = 1 / (q * B - r * A + s * z + t * y - u * x + v * w);
matrix.e[ 0] = ( f * B - g * A + h * z) * ivd;
matrix.e[ 1] = (-b * B + c * A - d * z) * ivd;
matrix.e[ 2] = ( n * v - o * u + p * t) * ivd;
matrix.e[ 3] = (-j * v + k * u - l * t) * ivd;
matrix.e[ 4] = (-e * B + g * y - h * x) * ivd;
matrix.e[ 5] = ( a * B - c * y + d * x) * ivd;
matrix.e[ 6] = (-m * v + o * s - p * r) * ivd;
matrix.e[ 7] = ( i * v - k * s + l * r) * ivd;
matrix.e[ 8] = ( e * A - f * y + h * w) * ivd;
matrix.e[ 9] = (-a * A + b * y - d * w) * ivd;
matrix.e[10] = ( m * u - n * s + p * q) * ivd;
matrix.e[11] = (-i * u + j * s - l * q) * ivd;
matrix.e[12] = (-e * z + f * x - g * w) * ivd;
matrix.e[13] = ( a * z - b * x + c * w) * ivd;
matrix.e[14] = (-m * t + n * r - o * q) * ivd;
matrix.e[15] = ( i * t - j * r + k * q) * ivd;
return matrix;
}
転置
「transpose」は「転置(行と列の成分を入れ替えること)」を意味する英語です。よくExcelで使われるので、ご存知の方も多いでしょう。1行2列の成分と2行1列の成分を入れ替え、1行3列の成分と3行1列の成分を入れ替え…、というように4×4成分全て転置します。
・サンプルコード「lib」→「Matrix3D.js」 transpose() {
var mat = new Matrix3D();
mat.e[ 0] = this.e[ 0];
mat.e[ 1] = this.e[ 4];
mat.e[ 2] = this.e[ 8];
mat.e[ 3] = this.e[12];
mat.e[ 4] = this.e[ 1];
mat.e[ 5] = this.e[ 5];
mat.e[ 6] = this.e[ 9];
mat.e[ 7] = this.e[13];
mat.e[ 8] = this.e[ 2];
mat.e[ 9] = this.e[ 6];
mat.e[10] = this.e[10];
mat.e[11] = this.e[14];
mat.e[12] = this.e[ 3];
mat.e[13] = this.e[ 7];
mat.e[14] = this.e[11];
mat.e[15] = this.e[15];
return mat;
}
筆者は、3D計算に使う行列のアフィン変換行列、射影変換行列、カメラ変換行列などの3D計算の公式を丸覚えしているわけではありません。どうせ各プログラミング言語で最初に1回実装するだけなので、公式を見たり他のプログラミング言語で書いたコードを移植したりするだけです。学校では公式を覚えなければなりませんでしたが、実社会の方が調べてでも出来れば良いのでやりやすいですね。
東大出身のインフルエンサーも「大学なんて学歴だけですぐ中退すれば良い。ネットで調べて分かるような歴史の年表なんて覚えなくて良い」というようなことを言っていました。
おわりに
今回は「行列」について解説しました。また、実際に行列を使って平行移動や回転や拡大縮小したり、カメラ視点を変換したり、遠近法で変換したりしてみました。
次回は「シェーダー」の文法について解説します。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- 「Krita」と「Python」でアーティスティックな絵を描こう
- 2D〜4Dで向きや大きさを持つ数字の集まり「ベクトル」について学ぼう
- 「WebGPU」でシェーダーを使って三角形を1つだけ描画してみよう
- HTML+JavaScriptだけでブラウザに図形描画(3)- Canvas API-
- 物理エンジン「Tiny2D.js」のソースコード詳説
- WebGPUライブラリ「UltraMotion3D」で3DのサンプルWebコンテンツを動かしてみよう
- JavaScriptで簡易物理エンジンを実装する
- オブジェクト指向で作った15パズルの完成
- Kinectで手の動きに合わせてモニタ上の画像を動かすサンプル
- パースペクティブの拡張