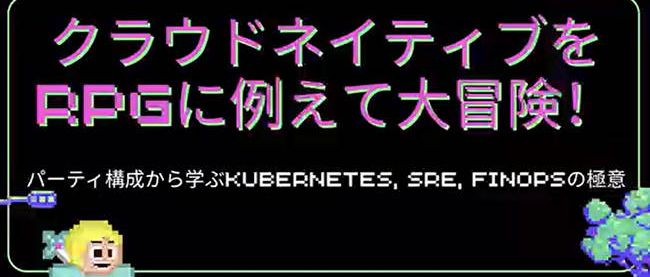ビジネス視点からオープンソースに貢献する仕組みを解説する日立のOSPOのトップ、中村氏にインタビュー

「日本でオープンソースプロジェクトへのコントリビューションを増やすためには何が必要か?」を考えるためのインタビューシリーズ第4弾は、日立製作所の中村雄一氏のインタビューをお届けする。中村氏は第3弾に登場したKeycloakのメンテナーである乗松隆志氏の上司でもある。
※注:田畑氏はオライリージャパンから出版されている「実践Keycloak」の訳者でもある日立製作所のエンジニアである。
中村氏は日立製作所のOSPO(Open Source Program Office)を立ち上げた人物でもあるが、何よりも「企業に所属してビジネスのためにソフトウェア開発を行うと同時にオープンソースコミュニティにも貢献する」という仕組みを日立社内で作り上げた人物でもある。現実的な観点から言えば、企業に所属してオープンソースソフトウェアに貢献するというのは相反する可能性を多分に含んだ要件である。なぜならオープンソースの消費者として社内のシステムやビジネスの中にオープンソースソフトウェアを組み込んで「ライセンスが無償でサポートフィーも要らない、定期的に開発が進み、脆弱性も解消してくれる」便利なツールとして使うことが社内で歓迎されたとしても、「業務時間内に自社のビジネスに関係ない修正を行うことや他者が書いた自社には関係のないパッチをレビューする」ということを容認できる経営者や管理職は少ないからだ。
しかし第3回のインタビューで乗松氏は「最初から日立としてオープンソースをやる、そして単に使うだけではなくプロジェクトに積極的に入っていってその中で存在を認められるようにならないといけない」という仕組みができ上がっていたと発言している。その仕組みを作り上げた中村氏に直接訊くことで、その背景や将来の構想を聞いた。
●参考:Keycloakのメンテナーに訊く、日本の大企業でOSSへのコミットを仕事にするには?
中村さんは日立のOSPOの人でもありますが、何よりも社内のエンジニアがオープンソースに貢献するということを日立のビジネスとして成立させた人物と私は認識しています。そこに至る経緯をまず教えてください。
中村:私、今のKeycloakに関わる前にはSELinuxの開発をやっていたんですね。その前は国際標準のプロトコルの開発とかをやっていました。SELinuxの失敗を今のKeycloakのビジネスに活かしているというのが簡単な経緯になります。もう少し細かく言うとSELinuxの開発をやっていてどうやったら草の根のエンジニアの趣味ではなく「ビジネスとして関われるか?」を考えていました。それは日立の社員としてアメリカに留学している時だったと思いますが、いろいろな会社にアプローチをしたんですね。で、究極的にはSELinuxをやるならお客は米軍で、米軍と仕事をするならアメリカの市民権がないとダメということがわかったんです。
ビジネスでやるというのはつまりエンジニアが給料を貰ってSELinuxを開発するということですね?
中村:そうです。でもそのためにはとても大きな壁、アメリカの市民権というのがありまして(笑)。で、日本に戻ってきてから何かビジネスとしてやれるモノはないか? を考えていろいろ探していた時に「API管理」というのが日立社内で盛り上がっていまして、それはおもしろそうだと。でも他にビジネスとしてはまだ誰もNo.1になっていない大きな空白地帯があるのがわかったんですよ。それが認証だったんです。
SELinuxの時にわかったのは、ソフトウェアの世界ではニッチであってもナンバー1にならないとダメだということです。その時に「どこならナンバー1になれるか?」を探して見つけたのがAPI管理と認証という領域だったわけです。認証はこれから多くの企業がオープンな認証システムに移行していくことが見えていましたし、すでにヨーロッパの銀行で使われることがわかっていたんですね。日本は海外から遅れること大体3~4年でその波がやってくるので、そこにナンバー1になるチャンスがあると。
その時にRed Hatのエンジニアが開発していたソフトウェアをKeycloakという名称でオープンソースとして公開していることを知ったんです。その中身を見てみたら、まだベータ版と言うレベルでしたね。しかし認証のソフトウェアでしたがAPI管理の中でも認証は必須なのでちょうどAPI管理と認証が交わる領域をカバーできることがわかったんです。それでこのソフトウェアに賭けてみようと思ったんです。その時、社内で経験があって異動できる感じの立場にいた乗松さんに出会って、彼をこのプロジェクトに引き込もうと思って声を掛けて一緒に仕事を始めて、最初にやったのはKeycloakのリポジトリにプルリクエストを送ることだったと思います。
中村さんは草の根のエンジニアが偶然出会ったオープンソースに貢献するというのが持続しないということを認識して、ではビジネスとしてやるなら持続するのでは? と思ったということですね? さらにソフトウェアの世界ではその領域で世界でトップにならないとダメだというのがわかったと。その上でじゃあどこならまだ誰もトップになっていない領域があるのかを探して、そこに注力したという経緯ですね。それはどちらかと言うとオープンソースありきではなくビジネスありきの発想ですよね。
中村:そうです。私はSELinuxの時の反省から何よりも日立のビジネスとしてやるということをまず考えてどこに空白があるのか、そこでナンバー1になれるのか、を考えたわけです。なのでいろいろな要素を組み合わせて「ここなら成功する!」を作り上げるプロデューサー的な発想ですね。
その要素として分野として認証やAPI管理があり、人材としての乗松さんがいて、ソフトウェアとしてRed Hatが主幹となっていたKeycloakがあった、それを組み合わせたということですね。それは草の根と言うよりもビジネス優先の発想ですよね。
中村:何よりも日立のビジネスとして成立するのか? ナンバー1になれるのか? が重要だったわけです。
それとオープンソースに貢献する、つまり自社のビジネスとは関係ない業務もそこに含まれるというのがポイントなんですが、それはどうやって納得させたんですか?
中村:それは自社のためのソフトウェア開発とコミュニティに向けたソフトウェア開発が分かれていないというのがポイントなんです。つまり、コレは自社のためのソフトウェア開発、ココからはコミュニティのための仕事と言う風に分離していない、どちらも自然に繋がっている、無理をしていないということです。The Linux Foundation(LF)の関連でいろいろなOSPOの人と対話していますが、上手くいっている企業はだいたい無理をしていないんですね。これは自社のため、これはコミュニティのためと分かれていなくて自然に無理なく企業の仕事とコミュニティの仕事が繋がっているという状態です。それはコミュニティの仕事をすることが、究極的には自社のためのソフトウェア開発の加速に繋がるということが理解されているからですね。
OSPOについてはインナーソースのためだとかオープンソースの脆弱性に関する相談窓口だとかいろいろ言われていますが、それはベースの仕事として重要であるものの、何よりも無理をせずに業務の中にオープンソースへの貢献を行うということを推進することが本来の仕事だと思います。
OpenStackの開発を行っていたNTTの水野伸太郎さんのコメントにありましたが、NTTでOpenStackのバグ修正をやってコミュニティに還元せずに自社内で溜め込んでいたのが150件になった時にこのままだとそのバグ修正が自社の利益ではなくてコミュニティのリリース、つまりUpstreamと整合性を取らないといけない負債になってしまう、だから知財の人を説き伏せて社員が書いたコードを公開するという方法に変わったという部分と相通じる発想ですね。
●参考:日本でOSSのコントリビュータを増やすには何が必要か? 座談会形式で語り合う(前編)
中村:そうです。オープンソースを開発することが、それを使う自社のためになるということを理解させたということですね。自社が使うソフトウェアの進化を加速させたいならそのソフトウェアの開発に協力する、つまりコミュニティに対して貢献する、具体的に言えば自分が書いたコードを公開する必要があるということです。
でも知財の人から言えば、「なんで社員が業務時間中に書いたコードを無償で公開するのか? それはひょっとすると特許になるんじゃないか?」みたいな話は出ませんでしたか?
中村:これは日立だけの状況かもしれませんし、多分に個人の感想になるんですが、弊社の知財は「コレをやったら絶対にダメ」というガイドラインを示して、現場が悩んだときにアドバイスをするという姿勢だと思うんです。だから現場が判断してコードを公開するほうがビジネスのためになると判断したならそれを尊重してくれる感じなんです。そもそもオープンソースとしてすでに公開されているソフトウェアに対して何か機能追加をしたとしても、それが特許になるというのは少ないとは思いますね。研究所で開発した画期的なソフトウェアをいきなりオープンソースで公開するというのとはレベルが違う話なので。
もう一度、話を整理すると「ビジネスとして持続できる領域は何か?」を探して「そこでニッチであってもナンバー1になれるソフトウェア」を見つけて、そこで「貢献を行えるエンジニア」を当てがって、「ビジネスのための開発とコミュニティのための開発を分けずに自然と仕事ができる」ようにして、「知財も納得」したということですね。それは草の根でエンジニアがたまたま見つけたオープンソースを社内で使って成功して、その流れで貢献する方向に持っていこうとする発想とはまったく別ですよね?
中村:CNCFの日本でのコミュニティでもあるCloud Native Community Japan(CNCJ)でも、趣味でオープンソースに貢献していますという草の根のエンジニアと偶にお会いします。そのエンジニアの個人のキャリアパスとしてそういうことをするのは良いとは思いますが、それでは持続しないなぁと。なのでエンジニアも単に自身のキャリアパスとしてオープンソフトウェアに関わって結果として転職できたでの良かったという例は分かりますが、会社のビジネスとしてやれるかどうか? はよく考えた方が良いと思います。そのオープンソースプロジェクトに貢献することが自社のビジネスに繋がる、つまり自社のビジネスを加速、ソフトウェア開発を加速するために必要なことを無理なく行えるために何を選べばいいのか? を考えるということです。
中村さんの発想が草の根ではなく何よりもビジネスがあって、その後にオープンソフトウェアがあるということがよくわかりました。そして知財に対する説得のポイントも参考になるかなと。中村さんはKeycloakの人でもありますが実はFinOpsの人でもあるんですが、FinOpsについても同じ発想ですか?
中村:そうですね。FinOpsもパブリッククラウドを使う時にどうやったら価値を最大化できるのか? をフレームワークとしてオープンソースにしているわけですよ。それを使ってビジネスにする、当然、そのビジネスを加速するためにFinOpsを使う、加速するためにはコミュニティに貢献しなければいけないということです。
中村さんの将来計画は何ですか?
中村:私は社会のインフラストラクチャーにもっとオープンソースを応用していく仕事をしたいなと考えています。実は電力とか水力とか鉄道とかというインフラストラクチャーは競争をする領域ではなくてみんなが協力しあっていくことで社会を良くすることができる領域だと思っているんですね。電力を送る配電というのは需要を見ながら電力を過不足なく供給することが必要で、ちょっと間違うと大規模な停電が起こってしまうというシステムですよね。そこでは1社が競争に勝って利益を独占するという発想ではダメなんです。そういうことをやっているのがLF Energyというグループなんですが、日立の社内、これはヨーロッパの人ですが、同じ発想の人を見つけまして。そういう人と共同でインフラストラクチャーにオープンソースを使うという仕事ができるともう日本がどうのとかいうレベルじゃない仕事ができるわけです。それこそグローバルにビジネスができる。そういう人を集めて世界規模で仕事をしたいと思っています。
中村氏の回答は非常に明確でビジネスとして持続することが最優先、そのために必要な要素を見つけて組み合わせて大きな仕事をするプロデューサー的な立ち位置であることが良くわかるインタビューとなった。自社が消費者として使うソフトウェアを加速するために業務としてコミュニティに対する貢献が必要だというのは、NTTの例にあったOpenStackの修正パッチを社内に溜め込んでも負債になってしまうという事例からもわかるようにオープンソースを利用する最初の段階から社内で合意を取っておくべき要点と言える。本稿が、草の根でオープンソースに貢献しようとしているエンジニアの発想転換のヒントになることを願う。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- クラウドネイティブ啓蒙のためのジャパンチャプター結成の背景をインタビュー
- 日立のOSSコントリビュータに訊いた組織のあり方と失敗談
- Keycloakのメンテナーに訊く、日本の大企業でOSSへのコミットを仕事にするには?
- Kustomizeのリードに昇格したエンジニアが語るOSSへの参加を持続させるコツとは
- オープンソースを活用する企業にオープンソースプログラムオフィスは必要か?
- Red Hatのシニアディレクターに訊くOSPO
- LFがOSPOのビジネス価値を調査したレポート「The Business Value of the OSPO」から読み解くOSPO設立の動機と役割
- IBMのJeffrey Borek氏にインタビュー。OSPOに関する課題と未来を考察
- 日本でOSSのコントリビュータを増やすには何が必要か? 座談会形式で語り合う(前編)
- LFがオープンソースにおけるDE&I(多様性・公正性・包摂)に関する調査レポートを公開、ほか