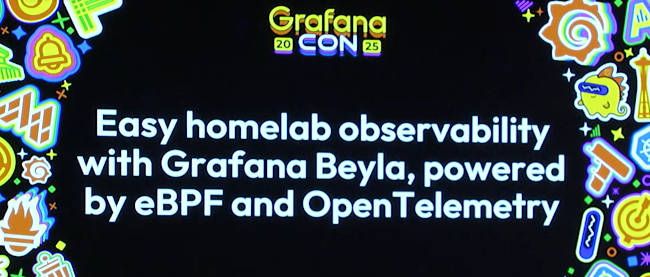GrafanaCON 2025、Grafana Labsのキーパーソンにインタビューを実施(後半)

GrafanaCON 2025から、キーパーソンへのインタビューの後半として、インタビューを実施した2025年5月の時点では入社後3ヶ月、Developer Program DirectorというタイトルのTed Young氏にインタビューを行った。Young氏は元Lightstep、元Pivotalという経歴を持つエンジニアだ。前半はGrafana Labsの共同創業者のTorkel Ödegaard氏、CTOのTom Wilkie氏へのインタビューである。
●参考:GrafanaCON 2025、Grafana Labsのキーパーソンにインタビューを実施(前半)
Youngさんはまだ入社して3ヶ月ということですが、前職は何をしていたんですか? またGrafana Labsに転職した理由を教えてください。
Young:以前はLightstepという企業でOpenTelemetryの開発をやっていましたが、2021年5月にLightstepがServiceNowに買収されてから状況が変わってしまったんです。買収直後は何も変わらずに同じ仕事ができていたんですが、徐々に変わってしまい、VPやエグゼクティブに「どうしてオープンソースプロジェクトに貢献するのか?」を毎回説明しなければいけないという面倒な状況になってしまいました。Grafana Labsに転職したのはそれが原因です。上司にオープンソースに貢献する必要性を毎回説明しなくて済むのは良いことです。
OpenTelemetryに関わるようになったのは、Lightstepの前に働いていたPivotalの時からですね。その当時はPaaSのCloud Foundryを開発していました。そのオブザーバビリティが使い物にならないということで毎回、欲求不満が溜まっていたという状況でした。その時にOpenTracingを見つけて分散トレーシングを実装していました。そのOpenTracingがOpenCensusと一緒になってOpenTelemetryというプロジェクトになったわけですが、その開発を引き続きLightstepでやっていたというわけです。
PivotalのCloud Foundryの話が出ましたので脱線しますが、SynadiaのNATSに関するドタバタ劇 ※はどう思いますか?
※注:NATSはCNCFに寄贈されたCloud Foundry由来のネットワークソフトウェア。その主な開発組織であるSynadiaがNATSに関するCNCFからの脱退と著作権の所在に関して争議を起こした。2025年5月の段階で解決している。以下参照。
●参考:Protecting NATS and the integrity of open source: CNCF's commitment to the community
Young:あぁ、SynadiaがCNCFに寄贈したNATSを自分達のモノとして取り戻したいというアレですね? オープンソースに関わっているエンジニアとしては残念としか言いようがないですね。
そもそもCNCFに寄贈した時点で著作権をCNCFに渡していなかったというのが発端らしいですが。
Young:でもCNCFのエコシステムに入って良いところを受け取っていながら、突然、プロプライエタリーなソフトウェアに戻して利益を取ろうとするというのは良くないとは思いますよ。いくらオープンソースでマネタイズするのが難しいとは言っても、例えばオープンコアにする方法論もあったはずなのに。今回の一件で感じるのはベンダーニュートラルなオープンソースプロジェクトというのが重要だということです。それをCNCFには強く提言したいですね。形だけはオープンソースプロジェクトに見えても、実態はベンダー1社がコントリビュータの過半数を占めていて方向性を決めるチーム、例えばTechnical Oversight Committeeなどが1社のエンジニアで寡占されている状況は健全ではないと思います。そういうプロジェクトがどれだけあるのかをちゃんと把握しておく必要がありますし、ユーザーもそれを理解しておくべきです。
今回の件はオープンソースでビジネスを持続させることの難しさを浮き彫りにしたと思います。
Young:それはその通りで、オープンソースを開発することでビジネスを持続させるのは難しいことです。多くの場合、オープンコアになりますがそれは良くないと思います。なぜならユーザーがオンプレミスで自社のデータセンターに入れるソフトウェアは、透明性やセキュリティの観点からコアだけではなくすべての機能についてオープンソースであるべきだと思うからです。それは企業から見ても当然の意見だと思います。セキュリティの観点からは、ある一部だけブラックボックスのソフトウェアが存在するというのは問題になると思います。
Grafana Labsはオープンソースの部分とクラウドサービスとして提供する部分を分けることによりクラウドでマネタイズを行い、オープンソースのエンタープライズ版を作る必要がないような仕組みを使っています。この方式は今のところ、上手くいっていると思います。OpenTelemetryの話をしますと、OpenTelemetryはデータの形式などは公開された標準の形で誰もが使えますし、そこに改良を加えられる形になっていますが、データストアと分析の手法については定義していないんです。そこにさまざまなベンダーが独自の特色を加えたソリューションを開発してマネタイズすることが可能になります。
クラウドサービスとオープンソースの使い分けが上手くいっている例ですよね。オープンソースを語るGrafanaCONとGrafana LabsのサービスであるObservabilityCONを分けているのもわかりやすいと思います。順番が逆になりますが、Youngさんのタイトル、Developer Program Directorというのは何なんですか?
Young:良い質問ですね。Developer Program Directorっていうのはどんな仕事だと想像しますか? よくわかりませんよね?(笑)。私もこのタイトルでは何の仕事かわからないと思います。私の仕事はデベロッパーを助けることですが、特にOpenTelemetryのコミュニティとGrafana Labsのデベロッパーの方向性を合わせるというのが大きな仕事です。OpenTelemetryへの貢献をしているのはGrafana Labsのエンジニアの他には主なパブリッククラウドベンダー、オブザーバビリティベンダー、そしてエンドユーザーが主体です。ベンダーの貢献が大きな部分を占めますが、エンドユーザーもデベロッパーとして貢献しています。
エンドユーザーは一部の機能を実装したいとか特定のバグを直したいというような貢献の仕方になります。そうしたエンドユーザーにはAtlassianやShopifyがいます。そういうユーザーとベンダーが協調して同じ方向性で仕事をするように調整することですね。
最近オブザーバビリティベンダーは、生成AIを使っての機能強化に注力していますが、OpenTelemetryとしては何か変化はありますか?
Young:最近、コミュニティの中に生成AIに関するワーキンググループができました。その中でいろいろ議論が始まっています。ただ生成AIとは言ってもニューラルネットや機械学習、LLMを使う部分に関しては新しい技術ですが、システム全体から見ればまだ多くの部分が従来型のプログラミング言語で書かれていますし、そのシステムとの連携を考えないといけないという部分は残ります。
最後にYoungさんにとってのチャレンジはなんですか?
Young:そうですね、タスクをいっぱい抱え込まないことですね。これはプロジェクトがまだ若い時点ではそれほど難しい問題ではないんですが、プロジェクトが成熟してくるとやらなければいけないことは増える一方になるので、優先順位をちゃんと付けて実行していくことが重要になります。そのためには「そのプロジェクトにとって何が重要なのか?」をバリュープロポジションという形で明文化しておくことが重要です。そこがブレてしまうと、そのコミュニティに参加しているエンジニアも迷ってしまうわけです。OpenTelemetryのバリュープロポジションは非常に明快なのでコントリビュータが迷うことはないと思います。Kubernetesのプロジェクトの早い段階ではさまざまな要望や思惑が出てきてベンダー間の誤解や迷いが発生したことを記憶していますが、ああいった状況を避けることが重要だと思っています。
SynadiaのNATSを巡るドタバタ劇については、NATSを使う立場にいたPivotalのエンジニアらしく熱く語る口調が印象的なTed Young氏のインタビューだった。オープンソースとクラウドサービスの切り分けについても明確に解説を行い、他のSaaSのオブザーバビリティベンダーとの差別化を明確にしたインタビューとなった。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- GrafanaCON 2025、Grafana Labsのキーパーソンにインタビューを実施(前半)
- GrafanaCON 2025開催、最新のGrafana関連の情報を解説。キーノートから見るリアルな運用現場に対応したAIアシスタントとは?
- GrafanaCON 2025、インストルメンテーションツールのBeylaを解説するセッションを紹介
- KubeCon Europe 2025、Dash0のCTOにインタビュー。野心的な機能の一部を紹介
- KubeCon North America 2024から、分散アプリのフレームワークNEXを解説するセッションを紹介
- Observability Conference 2022開催、Kubernetesにおける観測の基本を解説
- KubeCon NA 2021プレカンファレンスのWASM Dayの後半を紹介
- GrafanaCON 2025から、スキポール空港のキオスク端末のオブザーバビリティを解説したセッションを紹介
- 「Grafana Cloud」の先進的ユーザーであるグリーが10年をかけて到達した「オブザーバービリティ」とは
- Grafana Labs CTOのTom Wilkie氏インタビュー。スクラップアンドビルドから産まれた「トラブルシューティングの民主化」とは