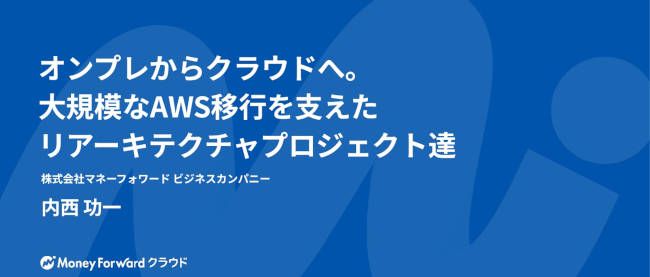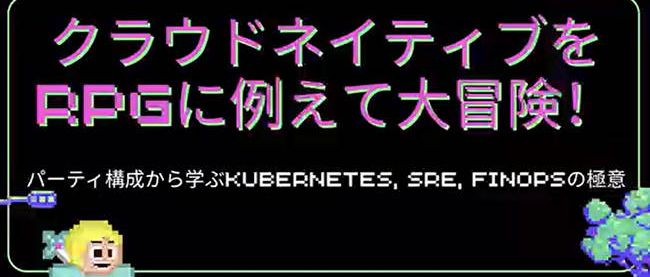LFが「オープンソースAIにおけるグローバルな協業のための戦略的方向性の策定」日本語版を公開

こんにちは、吉田です。今回は、Linux Foundation(LF)が公開した、2025年5月にパリで開催された「2025 GOSIM Open Source AI Strategy Forum」の主なハイライトと、今後のオープンソースAIの展望をまとめた「オープンソースAIにおけるグローバルな協業のための戦略的方向性の策定」の日本語版について、内容を紹介します。
【参照】オープンソースAIにおけるグローバルな協業のための戦略的方向性の策定 日本語版を公開
https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/08/gosim-2025-jp/
「2025 GOSIM Open Source AI Strategy Forum」のハイライト
このイベントは、Eclipse FoundationとGOSIM(Global Open- Source Innovation Meetup)が共催したイベントで、産業界、学界、市民社会、オープンソースコミュニティ、およびオープンソースFoundation のグローバルな専門家が集まり、「オープンソースAI」さまざまな議論が行われました。
その中で、「オープンソースAI」エコシステムが直面する課題として、以下のものが挙げられました。
- 「オープンソース AI」に関するコンセンサスの欠如
- 地政学的・規制上のリスク
- オープンソースAIの経済的持続可能性
- 企業におけるオープンモデルの採用
また、「オープンソースAI」エコシステムに関する提言として、以下のものが提示されました。
- オープン性を推進する
- AI におけるグローバルなコラボレーションの促進
- オープンソースAIがデジタル主権に与える可能性
- 再現性と研究の実現
- オープンソースAIの企業導入を促進する
- 責任あるAIのプラクティスの推進
詳細については、後ほど紹介したいと思います。
「オープンソースAI」エコシステムは近年驚異的な成長を遂げています。Hugging Face Hubには現在150万を超えるモデルが登録されており、その中には数億回ダウンロードされているものもあります。2025年1月に公開されたDeepSeekは、OpenAIと同等の性能を持つだけではなく、その開発プロセスの詳細を論文で公開したことで、世界中のAIコミュニティに衝撃を与えました。
その後も、さまざまな研究機関がオープンソースのLLMをリリースし、プロプライエタリモデルとの差を縮めてきました。直近の話題ではOpenAIが「gpt-oss」を公開したことです。gpt-ossはこれまでのGPTシリーズとは異なり、モデルの重み(パラメータ)が公開されているため、誰でも自由にダウンロードして自身の環境で実行、改変、再配布することができます。また、以下のような点で画期的とされています。
- オープンソース: ライセンスは「Apache 2.0」を採用しており、商用利用も含め、非常に自由度の高い活用が認められています。これにより、企業や個人が独自のAIサービスを開発しやすくなります。
- 高い推論能力: 各種ベンチマークテストにおいて、同規模の他のオープンソースモデルを上回る高い性能を示しています。特に、複雑な問題の解決や思考の過程(Chain-of-Thought)を提示する能力に長けています。
- ツール利用: WebブラウジングやPythonコードの実行といった外部ツールと連携する機能を持ち、単なる文章生成に留まらない、より高度なタスクを実行できます。
- ローカル環境での実行: 特に「gpt-oss-20b」は比較的少ない計算資源で動作するため、クラウドサービスを利用せずとも手元のPCでAIを動かすことができます。これにより、プライバシーの懸念なくデータを扱えたり、開発の自由度が高まったりします。
- 思考プロセスの透明性: AIがどのように結論に至ったかの思考プロセスを確認できるため、開発者はモデルの挙動を理解しやすく、デバッグや改善が容易になります。
やはり、どうしても大きな話題となるのは「オープンソースAI」に関する定義かと思います。オープンソースの定義で重要な点は、4つの自由(使用、研究、改変、再配布)をほとんどの「オープン」なAIは順守しているとは言えません。したがって、これらに対する共通認識を確立することが不可欠であるという意見がありました。
オープンソースAIの展望を示す
「オープンソース AI 定義(OSAID) バージョン 1.0」
ここでは、オープンソースイニチアチブが発表した「オープンソース AI 定義(OSAID) バージョン 1.0」をベースに議論が展開されました。OSAIDでは、AIシステムがオープンソースとみなされるためには、そのシステムおよび構成要素が個人が許可なく使用、研究、改変、再配布できる4つの自由を認める条件の下で提供されている必要があることを重視しています。
特に、オープンソースの定義(#2)の要件「ソースコードは、プログラマーがプログラムを変更する際に好ましい形式である必要がある」をAIシステムに適用しています。この要件を満たすため、モデルパラメーター(事前学習された重みとバイアス)、トレーニングデータの前処理コード、AIシステムのトレーニングと実行のためのコード、およびトレーニングデータ自体(それが不可能な場合、十分な詳細な情報)は、すべてオープンソースライセンスの下で公開される必要があります。
しかしながら、このオープンソースの要件をすべて満たす必要があるかどうかは議論が分かれるところですが、早期にコンセンサスを構築必要があるという点や、オープンAIアセット(モデルにはOpenMDWライセンス、コードにはApache v2またはMITライセンス、データにはCC-BYまたはODC-BYライセンスなど)に対して、寛容的なライセンスの使用を促進することも今後必要なアクションであると提起されています。
このような課題についてさまざまな参加者の視点で議論が進められ、その後推奨するアクションとして提起されるという形式のこの文書について、「オープンソース」と「AI」との関わりについて、興味を持たれた方にお勧めのドキュメントになっています。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- LFがオープンソース活用等の計画を策定する「Open Source Congress」のレポートとCI/CDの最新状況に関するレポートを公開
- LFが分散型テクノロジーエコシステムのための統括組織「LF Decentralized Trust」の立ち上げを発表、ほか
- AI_dev Europe 2024から生成型AIのオープンさを概観するセッションを紹介
- プロジェクト支援、リサーチ活動、エンジニア教育など、年次報告書「The Linux Foundation Annual Report 2021」に見る、Linux Foundationの活動トピックス
- SigstoreコミュニティがGAを発表、OSSのベストプラクティスを学べる新トレーニング「オープンソース管理と戦略」日本語版をリリース
- LF傘下のFINOSがOSFFで金融サービス業界におけるOSS関連の調査レポート「The 2022 State of Open Source in Financial Services」を公開
- 日立とみずほがサプライチェーンファイナンスの実証実験を開始、LFが「オープンソースの管理と戦略」トレーニングプログラムを発表
- デジタル通貨やオープンソースAIなど、LF主催「Open Source Summit Japan」におけるJim Zemlin氏の講演を振り返る
- OpenSSFを拡大・支援するため1,000万ドルの新規投資を調達、「The 2021 Open Source Jobs Report」を公開、ほか
- 「Open Source Forum 2019」開催 ― キーマンが語る企業や社会の要素となるOSS技術とは