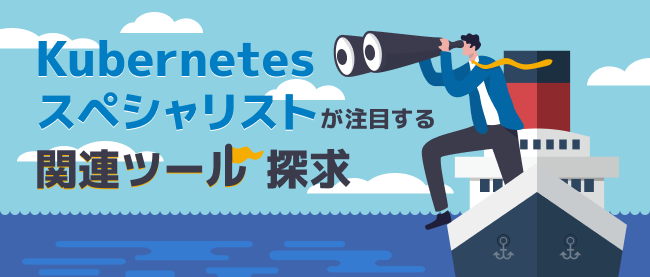「人と人との関係性」から新たな転機 ~先が見えない時代だからこそ、面白い方向を目指そう

今の時代、若手エンジニアが勉強したいと思えば、いくらでも教材や資料はインターネットで手に入る。だがそんな便利な時代であっても、やはり先輩たちの生きた経験に裏打ちされたアドバイスは貴重だ。本連載では、情報インフラ系SIerとしての実績の一方で、現場で活躍できるエンジニア育成を目指した独自の技術研修「BFT道場」を展開。若手技術者の育成に取り組む、株式会社BFT 代表取締役 小林道寛氏に、ご自身の経験に基づくスキルアップのヒントや、エンジニアに大切な考え方などを語っていただく。
「協調や調和」よりも
「自由と正義」を軸に、ものごとを見る
皆さん、こんにちは。株式会社BFTの小林道寛です。
この連載も、早いものでこれが最終回です。そこで今回は締めくくりとして、私が自分のキャリアを通じて大切にしてきたことなどを、少しお話ししたいと思います。
まず、よく聞かれるのは「エンジニアや経営者として、何を判断の基準にしているのか」ということです。特に経営者の場合は、いろいろな課題に対して「では、こうしよう」と判断を下すのが主な仕事と言っても良いでしょう。
では、私は何をよりどころ=判断軸にしているのでしょうか。よく冗談半分に言っているのが「自由と正義」です。相手は「なんだ、それ?」みたいな顔をして「経営者ならば、やはり『協調や調和』とかじゃないんですか」とツッコまれますが、私としてはかなり本気で「自由と正義」が一番ん大事だと思っているのです。
というのも、日本社会では「他者との協調や調和」が重視されるあまり、それがしばしば強制の空気になりかねないからです。最近SNSなどで「同調圧力」などと言われていますが、それが個人の自由な意思や考えを縛るのでは、むしろ逆効果です。
だからこそ一番大切なのは、やはり「自由と正義」。すなわち人それぞれの自由な世界観や、これが正しいとする信念こそが尊重されるべきだと思うのです。そうしてお互いを認めたうえで協調し合える部分を探っていけば、そこにまた何か新しいことが生まれてくるのではないでしょうか。
会社だって、ひたすら横並びを強制されて、若手が意見を言っても「出過ぎたまねをするな」と押さえつけられたら、とても「ここで頑張ってみよう」とは思えませんよね。
「人々に求められている自分」を知ることが
私にとっての「自分探し」
「自由と正義は分かったが、そもそもあなたの仕事をするうえでの信念って何なんだ」と言われるかもしれません。私の場合は信念というか、それを探すためにずっと持ち続けてきた「問い」みたいなものはあります。それは「自分自身が何者なのかを知りたい」~いわゆる「自分探し」を、今でもずっとしているような気がしています。
「10代の学生みたいだ」と思われてしまうかもしれませんね。でも大人になっても環境や立場が変われば、求められる役割や立場もどんどん変化していきます。
例えば、仕事ならエンジニアでもマネージャーになれば営業も見なければいけない。あるいは採用も担当しなくてはならない。仕事だけではありません。結婚して家庭では夫や親になったり、いろいろなことが求められてきます。そうした変化の中で、自分は何をどう理解して、どう行動していくべきかというのを、ずっと考えてきたのです。
とは言っても、私は「こんな人物になりたい」とか「こんな地位についてみんなから認められたい」といった野心を抱いて、それを大きく育てようというタイプではありません。では野心がないのかと言われると、そうでもない。ただし私にとっての野心というのは、自分自身の欲望ではなく、色々な人の夢や思いを背負って進むことで、自分の中に育っていくものだと考えています。
ちょっとカッコよすぎる言い方をしましたが、そういう意味では今の社長という立場も、まさにそれです。だから、大事なのは自分の好き嫌いよりも多くの人たちから信頼されることです。その信頼に応えて、今度は自分から何か~技術だとか利益だとか価値とか~を返していくことが、自分の中ではすごく大切になっています。
そう考えると「自分が何者なのか」というよりは、「人々に求められている自分とは何者か」を知ることが、私にとっての「自分探し」なのかもしれません。
人と人との関係性から
化学反応が起こり「調和」が生まれる
今回のような話をしていると「そういえば小林さん、大学では哲学を勉強したんだよね」などと、私の経歴を知っている人は聞いてくれます。でも、白状すると私は大学には入ったものの、ろくに出席していませんでした。入学して講義に出ているうちに「哲学と言ってもこれはただの歴史だ。全く面白くない」と失望して、2年目以降は全く学校に行かなくなってしまったのです。
それがたまたま3年目のとき、アルバイト先が一緒だった哲学科の友達が「君が学校に来ないんで、気にかけている友人がいる」と言うのです。それがきっかけでまた学校に行くようになり、同級生たちと話すうちに面白い人が大勢いるのに気づきました。私は最初に「哲学なんてつまらない」と拒絶してしまったために、彼らの存在まで見落としていたんですね。
この経験がヒントになって、人は自分の狭い価値観だけで他者を見ると、非常に排他的な感情を抱く危険がある。だからもっと、人と人との間に何らかの力~コミュニケーションのようなダイナミクスが生まれる関係性を築けるように、ポジティブな気持ちで接するべきだと考えるようになりました。
例えば、最初から「哲学も同級生たちも、つまらない」と決めつけたら、そこで自分の周囲の空間も時間も閉じてしまいます。まさに1年目の私です。それが友人に「同級生のA君が、君のことを心配してたよ」と聞かされて、「なんで学校にも出ていない自分のことを心配してくれるのか分からないけど、それなら自分もA君と話してみよう」という気持ちになる。ここに関係性の化学反応が起こり「調和」が生まれるのです。
このようにして他者への興味や関心が起こり、相手を理解していくという体験が私の中に積み重なって、私の大学生時代は豊かなものになっていきました。そんなわけで、私は哲学については何も語る資格がありませんが、哲学科の仲間という代えがたい価値を手に入れたし、その素晴らしさを若い人たちに語ることはできると、ひそかに自負しているんです。
「遠くを見る」習慣をつけることが
キャリア構築の未来を確かにする
つい若い頃の思い出話ばかりしてしまいましたが、今の私は経営者として当社の社員を育て、支えていく大事な役目を与えられています。もちろん他の企業の社長さんたちも同じで、顔を合わせると「若手エンジニアがキャリアで迷ったときに、どう指導していけば良いだろう」といった話になることもしばしばです。
それについて私が1つ大事だと思っているのは「普段から少し遠くを見る習慣や訓練を心がける」ということです。というのも、もともと人はそれほど遠くを見る習慣を持っていません。だからこそ、意識的に自分自身に習慣づけたり、トレーニングする必要があるのです。
これをエンジニアのキャリア形成という視点で語れば、行き当たりばったりではなく、どうスキルアップや経験値を積み重ねて、自分の思い描くエンジニア像にたどり着くのか。それを普段から意識して行動し、成果を出していくということですね。
実は、私はその教訓をある先輩エンジニアから学びました。彼は「10年を1つのスパンに区切って、20~50代の各10年間を自分にとってどんな時間にするか考えないといけない」と言うのです。すごくシンプルな考え方ですが、今でも私はよくこれを借ります。もちろん全てに応用できるわけではありませんが、十分に「遠くを見る=長期視点で何かを考える」助けにはなると思っています。
また、人は誰でも「今を起点に考える」という習慣は当たり前に持っています。でも、そのままだと目の前の仕事を必死でこなしているうちに気がついたら歳を取っていて、でもやっていることは10年前と同じ……となる心配もあります。
だからこそ「遠くを見る」習慣が大事なのです。例えば、20代の若手エンジニアが「30歳になるまでに1,000人月規模のプロジェクトを回せる実力をつけたい」と決めたら、そこから逆算して「今の自分はいつまでに何をするべきか」が見えてくる。そうやって具体的なマイルストーンが見えてくれば、今のまま勉強を続けるのか、もっと経験のある人に教わったり、新しいプロジェクトを経験する必要があるのか。道のりが明確になってくるほど、方向の精度も学ぶスピードも上がっていくでしょう。
ただし、目標の大小はそんなに気にする必要はありません。もちろん「でっかいプロジェクトを回したい」なら、それはそれで頑張れば良い。ただ、私自身は人と競争する意識は全くなく「自分を探し続けている」だけなので、その答えがきちんと出せれば成功だと思ってきました。だから若い方も「自分は何を目指していきたいのか」「それは自分にとってどんな価値があるのか」を、より大切にするのが良いと思います。
時代の変化を、むしろ「チャンス」として
生かしていく方が面白い
ここまで、私自身の経験を振り返ってきました。でも、現在の状況は私の修行時代と比べると大きく変わってきているのも事実です。テクノロジーはもちろん、それを取り巻くビジネスや社会、経済もグローバル規模で激しく変化を続けています。5年先、10年先が不透明な中で、自分なりに目標は立ててみたけれど「本当にその通りに進められるのか」という不安は、若いエンジニアなら誰でも抱いていると思います。
でも、だからこそ、この先10年は自分にとってどんな10年なのか? ~自分の思惑が及ばない、自分でコントロールできない偶然に人間は支配されています。その偶発性こそが、ときにはピンチになり、チャンスになったりするわけですね。その変化を追い求めていく方が面白いし、それをどんどん自分に取り込んで、チャンスとして生かしていく方が良いと私は思っています。
これは、若い方だけではありません。経営者である私自身もそうだし、自分で自分の将来を切り拓こうという人ならば、誰でもそう考えるべきでしょう。それに、どうせ分からないなら面白い方が良いじゃないですか。「やらずに後悔するより、やって後悔する方が良い」と、昔から言いますしね。
なんてエラそうなことを言いましたが、実はこれは若かった頃の自分に、もしできることなら伝えてやりたい言葉でもあるのです。若い頃は色々と考えても尻込みしたり、やっぱり無理だなと諦めてしまったことが数知れずありました。だからこそ「もっと突き抜けていくのを目指した方が良いぞ!」と言ってやりたい。可能性は、広げればもっともっと広がるぞと。もちろん、それは同時に現在の自分への戒めでもあります。
今後のテーマは
「次世代の経営人材をどう育てていくか」
この連載は今回でおしまいですが、私の仕事はこれからも続いていきます。そこで最後に、これから先、自分で取り組んでいきたいことを少しお話ししておきたいと思います。
まず重要なテーマとしては「次世代の経営を担える人材を、どう育てていくのか」が挙げられます。私も、いつかは分かりませんが、経営のバトンを次の世代にわたすときが必ず来ます。それまでに、どうやって激しい変化の中で経営を支え、成長を実現できる人材を育てるのか。実は、それがまだ分からないのです。
と言うのも、私は昔あるテレビ局の子会社に在籍していたのですが、当時の先輩たちはその後、グループの会社の社長など社会の中で影響力のある存在になっていかれたのです。それも大勢いる中の誰か1人だけではなく、ほぼ全員が出世して経営トップのような地位につきました。かくいう後輩の私も、その1人です。
でも、これって不思議ではないですか。なんでこんな人材が1か所に集まり、頭角を現していったのか。すごい人材育成プログラムがあったわけでも、その先輩たちが出世を目指してガリガリ勉強していたわけでもありません。そんなわけで私自身も、まだ明文化され、定型化された「経営人材の育て方」が見えていないのです。
もちろん、先輩方はどなたも非常に優秀だったので、その片鱗を私たち若い世代にいつのまにか伝えてくださったのかもしれません。でも、正直言ってその何が効果を発揮しているのか、凡人である後輩の私には見当がつきません。
そんなわけで、この先しばらくは、この素晴らしい先輩方が私たちに伝えてくださったことが何なのか、自分なりにじっくりと考えていこうと思っています。「何か見えない力」なんて言ったら非科学的と叱られそうですが、おそらくそれは言葉や数値で可視化できない何か ~今回ずっとお話ししてきた「人と人との関係性」にヒントがあるのではないかと、見ているところです。
この宿題の答えが見つけられたら、またいつかどこかで皆さんにご報告したいと願っています。では、それまでお元気で。長らくのおつき合い、本当にありがとうございました。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- 先行き不透明な時代だからこそ、ときには立ち止まって「自分の現在と未来」を考えてみよう
- 最初の仕事は「企業理念」づくり~「人とシステムを作る」と決めて歩んだ10年を振り返る
- 他業種の人たちと働く経験を通じて、自分のエンジニアとしての「引き出し」を増やそう
- 「バリバリのエンジニア志向」だった私が、気がついたら「企業経営者」になっていた理由
- エンジニアのビジネススキルは、いわば「オプション」自分の「やってみたい」と思うところを自由に選ぼう
- 毎朝Slackで送る「社員たちへの手紙」。続ける理由は、その先にある「人を動かすシステム」づくり
- どんな場所からスタートするにしても、まず「こうなりたい自分」を明確に決めておこう
- キャリアのスタート台に立ったら、まず仕事に取り組むための「マインド」をかためる
- 休日は自分の部屋で引きこもるのも良し。「オン-オフをはっきり分けてストレスをつくらない」
- エンジニアの成長に欠かせないのは「何かを面白がれる気持ち」を持っていること