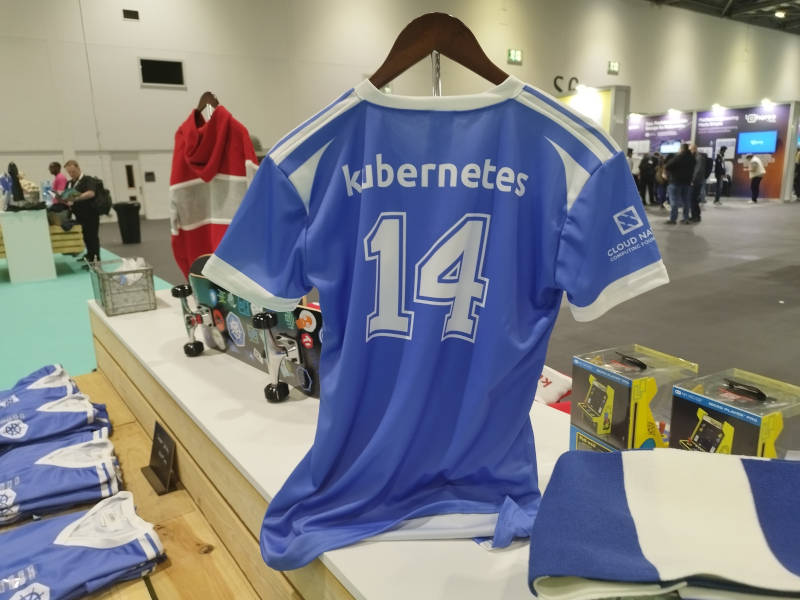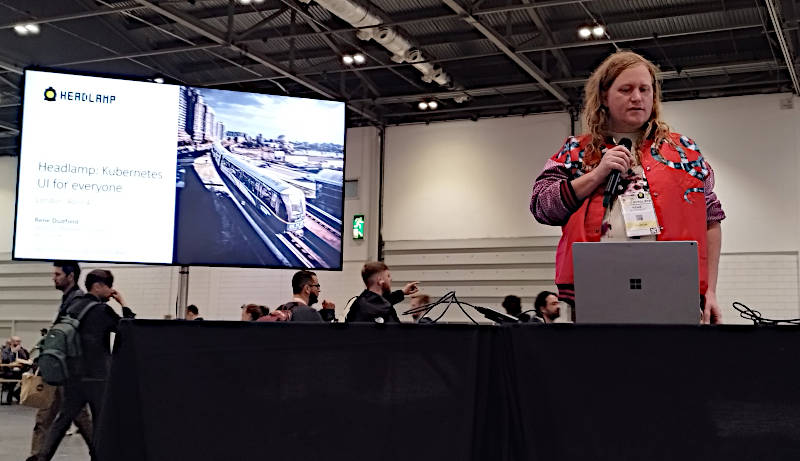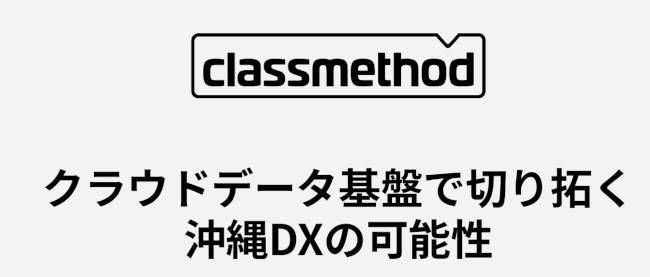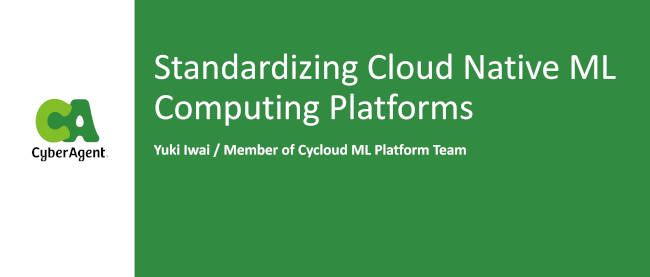KubeCon Europe 2025、ドコモイノベーションズのCEO秋永氏にインタビュー

KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025の最後の稿は、ドコモイノベーションズのCEO、秋永和計氏のインタビューをお届けする。ドコモイノベーションズはNTTドコモの子会社で、北米におけるドコモのR&D拠点であり、ビジネス開発の役割も担う企業だ。秋永氏はシリコンバレー在住で、北米で開かれるKubeCon North AmericaやOpenStack Summit、Red Hat Summit、AWSのre:Inventなどにも多数参加しているITカンファレンスのベテランとも言える人物だ。ちなみにこの稿では、カンファレンスの中で撮影した写真を文脈とはあまり関係なく紹介することとしたい。インタビューにおいて撮影に不備があったことが理由だが、ご容赦頂きたい。「写真で見るKubeCon+CloudNativeCon Europe 2025」だと思っていただければ幸いだ。
これまで何度もKubeCon North Americaではお会いしていますが、今回は秋永さんに全体の印象や、カンファレンスでおもしろいと思ったことなどを伺いたいと思います。まず全体の印象を教えてください。
秋永:私はアメリカに住んでいることもあって北米のカンファレンスには何度も参加していますが、ヨーロッパで開かれるカンファレンスというと2014年にパリで開催されたOpenStack Summitが最後だったような気がします。アメリカだといろいろなカンファレンスに行きますが、久しぶりにヨーロッパに行ってみようと。当時のOpenStack Summitは丁度、OpenStackが立ち上がる時だったような気がしますが、当時と今回のKubeConとはだいぶ状況が違いますよね。
そもそもOpenStackはNASAとRackspaceがAWSのインフラストラクチャーと同じ体験をオープンソースでやりたいということでソフトウェアを公開して、それを非営利団体を作ってホストするということから始まったんだと思いますが、結局、3大パブリッククラウドベンダーは乗らなかったんですよね。まぁ彼らにしてみたら、すでに個々に作っている仮想化基盤がサービスとして存在していたので、それをOpenStack化する必要性はなかったんでしょう。でもKubernetesはGoogleが社内のコンテナオーケストレーターであるBorgをオープンソースとして公開すると決めて、CNCFが創立されてコードを寄贈したことから始まっているので、GCPを始めとするパブリッククラウドベンダーも乗ったし他のベンダーもその流れに賛同してデファクトスタンダードになったということだと思います。
秋永:そうですね。今回ロンドンに来たのは、ヨーロッパでの状況を見ることが目的ですが、具体的には生成AIを含んでの動きに興味があったということです。
今回はCNCFのゴールドメンバーになったEricssonがキーノートを含めてかなり頑張っていた感がありますが、秋永さんの眼にはどう写りましたか?
秋永:すでに社内には報告していますが、Ericssonは確かに存在感を出していましたね。ただ全体的にヨーロッパのキャリアからは新鮮味のあるアナウンスがなかったような気がします。これまでだとBritish Telecomなどのキャリアがリードして新しいオープンソースソフトウェアを公開した、みたいなことが多数あったような気がしますが、そういうベンダー主導というのではない形になっているという。
他にはGoogleとByteDanceが一緒に今日のキーノートに登壇して、LLMのためのスケジューラーについて解説をしていました。アレを見て「もうGoogleからするとLLMや生成AIについて組むのは中国の企業になってしまったんだな」という印象を受けました。もう日本企業の出る幕はないと。アレについては?
秋永:私はそこよりもByteDanceっていうところがポイントかなと。つまり今、アメリカではTikTokで生成されているデータを中国が使うということに懸念があるということで、アメリカ政府ではアメリカのTikTokを中国から切り離すかどうかの議論がずっと続いていて、その視点からするとあの連携はGoogleとTikTokのアメリカ法人なんだろうなと。
ただセッションの内容自体はLLMのスケジューリングでデータそのものの話ではなかったですね。
●参考:KubeCon Europe 2025、3日目のキーノートでGoogleとByteDanceが行ったセッションを紹介
秋永:そうですね。でもTikTokが実際にLLMを巨大かつヘテロなGPUクラスターで実行しているからこそアレが出てきたわけで、実際に現場で使っていて発生した問題点に対してGoogleと一緒に解決しようとしているわけですよね。
そうだと思います。そういうリアルな問題をなんとかしようというのが2024年に香港で開催されたKubeCon Chinaでいっぱい出ていましたよ。単に生成AIをやってみたみたいな簡単な話ではなく、実際にビジネスで使って出てきた問題点をこうやって解決した、GPUのスケジューリングからGPUのフェイルオーバーまで実際にリアルで使っているからこそ出てくる話なんですよね。今回、ロンドンで会った日本人には「生成AIのリアルな問題に触れたかったら香港に行ったほうが良いよ」という話は何度もした気がします。
秋永:中国というのは規模がすさまじく大きいというところが日本とは圧倒的に違うわけですよ。私もドコモでデータマイニングのシステムをやっていてそれを海外で発表した時にChina Telecomの人からコンタクトがあって、ちょっと話を聞かせて欲しいというので打ち合わせをしたことがあります。その時に日本だと分析はこうやって~みたいな説明をしていたら、向こうは中国全体をターゲットにしたいって言うんですよ。よく聞いたら中国の一つの省だったかな? それひとつでほぼ日本全体の規模と同じなんです。向こうからしたらドコモのやってるのはこの規模なの? みたいな話になって「これは規模感が違う」って驚いた記憶があります。それぐらい中国というのは規模が大きいんです。だから純粋にテクノロジーの観点から言えばやりがいのある相手ではあるんですが、でも組む相手としてはいろいろあって難しいんですよね。
オープンソース的にはエンジニア同士が繋がって対話が始まって質問を投げ合っているうちにじゃあ、一緒に開発してみようか? みたいにはなるんだろうなとは思いますが、政治的な話が絡むと途端に難しくなるのはわかります。
秋永:ですね。エンジニアレベルの話ではなくなってしまうんです(笑)。
もうすぐ日本で初のKubeCon Japanが始まりますが、それに対する期待は? 何がどうなればKubeCon Japanは成功だったと言えるんでしょうね?
秋永:ロンドンでもKubeCon Japanをどうやって盛り上げるのか? というセッションがありましたし、私もその当事者とも話をしましたが、日本人のためのKubeCon Japanじゃなくて、世界に向けてどう発信していくべきなのか? 世界のコミュニティとどうやって付き合っていくのか? という観点が必要だと思いますね。
具体的にはコントリビューションを増やせるか? ということですね。それは難しい。日立の中村さん(KeycloakのメンテナーでCNCFのガバナンスボードのメンバーでもある中村雄一氏)ともパリでもロンドンでも話をしましたが、スポンサーではなくてユーザーからのコントリビューションを増やすというのは至難の業だと思います。あとCNCFは意図的だと思いますが、KubeCon開催のためのコミッティーの中の人を替えて新陳代謝させているんですが、日本の規模だと同じ人がやらざるを得ないというのが実態だと思います。これもコントリビュータが増えてないことの弊害だと思います。
秋永:それについては新陳代謝すべきもすべきじゃないも両方理解できるんですが、常識的に言って今の日本の事業会社、これはITベンダーを除いてという意味ですが、ではサイバーエージェントの青山さんみたいな人って存在し得ないんだと思うんですよ。
オープンソースに貢献してこういうカンファレンスに参加するという人、という意味ですか?
秋永:そうです。それはOSPO(Open Source Program Office)も同じでかなりの大企業にならないとそういう人材や組織を維持できない。どうしても日本の企業だとオープンソースは消費者としての立ち位置になってしまうと思うんです。ドコモだってオープンソースを使って開発するのは当たり前なのに、どうしても消費者的な発想が抜けないんですね。あとやっぱり出てくるのは知財問題。これはオープンソースにコントリビューションしてるけど、それは社員が書いているコードなので自社の知財なんじゃないの? って知財に言われたら返す言葉がないという問題ですね。
それについては2024年の年末に座談会をやった時にNTTの水野さん(水野伸太郎氏)が言っていたことが参考になると思うんですが、OpenStackに対してNTTがバグを直したりして積み上げていったプルリクエストが150個くらいになった時に「これはOpenStackを魔改造していることになっている」と気が付いてUpstreamに戻すように社内を説得して実施したという話があります。つまり自社のエンジニアが自社のためにソースコードを改造してもUpstreamに戻さないとその改造がバージョンアップのたび、永遠に面倒を見なければいけない技術的負債になってしまうという話です。
●参考:日本でOSSのコントリビュータを増やすには何が必要か? 座談会形式で語り合う(前編)
秋永:知財というのは社員が作ったものを守るのが仕事の組織なので、そもそも作ったものを無償で公開するというのとは真反対なんですよね。そこをちゃんと理解して戦略的に動いてもらうようにしないといけないということです。これは生成AIにおいても、すでに問題としてちらほら出てき始めている気がしています。そもそも生成AIのデータに著作物が使われる可能性について社内で議論が始まっています。生成AIはこれからどんどんと使われていくと思うので、どの会社でも将来的に揉める可能性があると思いますね。
秋永さんが見たかった生成AIについてはいかがでしたか? オブザーバビリティに生成AIを使うというのはオブザーバビリティのベンダー各社から出てきていましたが。
秋永:オブザーバビリティの中で生成AIというのはもう実際に使えるようになりつつある、というか単にエラーが発生したらそれを説明させるみたいなのは当たり前で、それをさらに進めるとどこまで行くのか? についいては興味がありますね。他にはストレージに生成AIをボルトオンするとかエッジに生成AIを入れるみたいな応用があるのかと思いましたが、それほど見付けられなかった感じでした。
これだけ参加者も多くセッションも多いとなかなか全容を把握するのは難しいですよね。もうご縁があるかないかになってしまうっていう(笑)。
ここには書き切れない多くのトピックに脱線しながらも、北米とヨーロッパから始まり中国、日本に視点を移しながら、生成AIや知財問題、ヨーロッパのCRAなどについても多くの問題意識を持っている秋永氏との対話となった。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- KubeCon Europe 2025、LF傘下になったOpenInfrastructure FoundationのJonathan Bryce氏にインタビュー
- KubeCon NA 2022、日本人参加者による座談会でWebAssemblyの未来を読む
- KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025から初日のオープニングキーノートを紹介
- KubeCon Europe 2025、3日目のキーノートでGoogleとByteDanceが行ったセッションを紹介
- KubeCon Europe 2025、MCPとCRAに関するセッションを紹介
- KubeCon North America 2024、日本からの参加者を集めて座談会を実施。お祭り騒ぎから実質的になった背景とは?
- Kustomizeのリードに昇格したエンジニアが語るOSSへの参加を持続させるコツとは
- 写真で見るKubeCon+CloudNativeCon North America 2024
- WASM Meetup@ByteDanceで垣間見たWebAssemblyの静かな広がり
- KubeCon Europe 2025、DynatraceのDevRelにインタビュー。F1でも使われているオブザーバビリティとは?