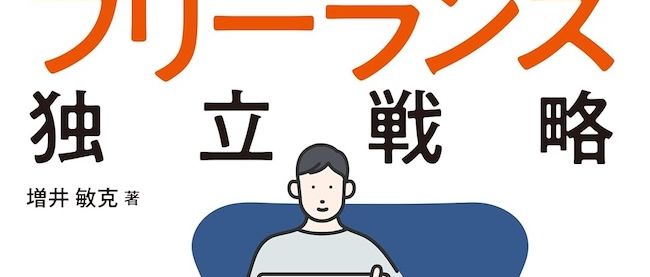女性エンジニアが語る「なぜこの道を選んだのか?」 ~ものづくりの楽しさから始まった3人のストーリー

「ITエンジニアが語る いまどきのエンジニア キャリア事情」と題して、レバテック株式会社へのインタビューを元に、3回にわたってITエンジニアの転職最前線を紹介していく本連載。第2回目の今回は「女性エンジニア」にフォーカスを当てていく。「知識や能力に性別は関係ない」と言われるITエンジニアの世界だが、実際はどんな特色や課題があるのだろうか。同社でQAエンジニアとして活躍中の3名に伺った。
理系・文系を超えて
「ものづくりの面白さ」を出発点に集まった人たち
今、IT業界で働く女性エンジニアは着実に増えている。その背景には男女機会均等法などの社会的な制度変革や少子化による人手不足など複数の要因があるが、いずれにしても、かつては「男性の職場」と思われがちだった世界にも女性の活躍する場が広がりつつあるのは、誰もが認めるところだろう。では、3人の女性がエンジニアという仕事を選んだ理由や経緯はどんなものだろうか。
まず、現在レバテックでデジタルイノベーション事業本部のエンジニアリーダーを務める樋口 ゆきの氏は、女子大の情報学部出身だ。と言っても文系の情報学部なので、プログラミングは在学中に「かじった」程度だという。それが、あえてQAエンジニアへの道を選んだ理由は何だろうか。
「大学で少しプログラミングをやってみて、その経験を生かしたいと思ったのですが、いわゆるゴリゴリの開発よりも、できあがったものをより良くしていくQAの仕事に強い魅力を感じました。ゼロからイチを作るよりも、イチをニにすることの方が自分には楽しいという思いがあったのです」(樋口氏)
この「イチをニにする楽しさ」という表現は、QAエンジニアという仕事の本質をみごとに言い当てている。たしかに開発はエンジニアの「王道」だが、道はそれだけではない。そうした多様性への気づきが、彼女をこの世界に導いたと言っても良いだろう。
続く坂田 明穂氏は、国際系の大学という、ITとはまったく違った角度からエンジニアの世界に入ってきた。理由は2つある。まず、大学では英語を活かした海外駐在のようなキャリアを期待されていたが、「そこにピンとこなかった」こと。そしてもう1つの理由が、ITに進む直接のきっかけとなったという。
「学生生活を振り返ってみて、何が楽しかったかなと考えたとき、大学のサークルでホームページを作って公開してみて、意外にものをつくる過程が楽しいなと感じたのを思い出したのです。それがきっかけでIT業界に興味を持って調べたら会社の選択肢も幅広くあったので、これは飛び込んでみようと思いました」(坂田氏)
最後の大森 由羽希氏は、さらにITから遠い場所からやってきた。大学の農学部から大学院に進んだが、2年生の時にコロナ禍が発生。農学系の就職先として定番の食品や製薬企業への道が狭まる中で、まったく新しい道を選択したという。
「ただでさえ研究職は狭き門で、しかも古い会社が多く、女性の研究職の採用は1割にも満たない状況でした。そんな中で『手に職をつけて働いていきたい』と考えたとき、エンジニアという選択肢が浮かんできたのです。もともとゲームが好きで、簡単なゲーム作りツールを触った経験もあり、ものづくりへの興味がすごくありました」(大森氏)
3人に共通しているのは「プログラミング経験がほとんどない」ことに引け目を感じず、自分の行きたい道を選んだということ。もう1つは「ものづくりの楽しさ」が、そうした気持ちの原点にあったことだ。このことは今現在、エンジニアを目指そうかどうか迷っている女性たちに、大きな勇気を与えてくれるのではないだろうか。
「女性だから」の課題だって
前向きに立ち向かえば乗り越えられる
今の日本のビジネス社会は男女機会均等が建前とはいえ、日々のニュースには、いまだ性別に起因するさまざまな課題が見え隠れしている。では、女性エンジニアは、実際のところ仕事の現場で「女性であること」をどの程度意識するのだろうか。この質問に対する3人の答えは、予想以上に前向きなものだった。
「私はあまり性別を意識したことがないです」と言う樋口氏に続いて、坂田氏も「私も感じたことはないですね」、大森氏も「私もあまりないです」と異口同音に言う。特にリモートワークが中心となった現在、性別による違いはさらに感じにくくなっているという。とはいうものの、まったく課題がないわけではない。大森氏は、ある状況下で経験した「微妙な問題」について指摘する。
「1対1だと特に性別は意識しないのですが、もし7~8人の中規模のチームで、しかも全員が年上の男性だったら、軽く見られる可能性はあると思います。実際に前職では、そういうチームで自分の言うことを聞いてもらえないことがありました。もっとも年下の女性だからなのか、単に私が経験不足だったからなのか、今となっては分かりませんが」(大森氏)
特にエンジニアの場合、スペシャリスト思考の強いエンジニア=いわゆる職人肌の男性上司だったりすると、何を言っても自分の考えを押し通されるといったこともある。だが大森氏の場合は、これをネガティブに捉えるのではなく「ゲーム感覚」で攻略していったと振り返る。
「私の場合は、運が良いことに周囲の方が根っからの悪人タイプではなくて、関わり方を工夫すれば攻略できる人が多かったのです。この人はどうやったら言うことを聞いてくれるか、気持ちよく仕事をするにはどういう準備をすれば良いか…ゲームの攻略を考えるように、楽しみながら関係を改善していきました」(大森氏)
一方、樋口氏は、苦手なタイプだからこそ、自ら積極的にコミュニケーションを仕かけて壁を乗り越えたと明かす。
「前職で、理詰めで来るタイプの上司がいました。どう詳しく説明しても『でも、それは違う』とひたすら詰められる。正直、苦手だったのですが、だからこそ直接話しかけに行って、『これは、どういう意図でこういう質問をされているんですか?』と聞いたりして、最終的には仕事以外のプライベートな話もできるまでになりました」(樋口氏)
外資系企業では、また少し事情が違ってくる。坂田氏は、自身が経験した「女性ならではのキャリアの壁」について、興味深い分析を示す。
「その外資系企業では、女性の活躍を後押しするということで、一時期、女性だから給料を上げるといった謎の制度がありました。それはダイバーシティ推進という長期的視点では意義があるのかもしれないけれど、逆に女性は個人として見られているのかという、モヤモヤした気持ちがぬぐえませんでした」(坂田氏)
カテゴリや集団としての「女性優遇」ではなく、「私という個人」の能力を正当に評価してほしい。こうした坂田氏の思いは、多くの女性エンジニアの抱いている気持ちを、かなり的確に代弁しているのではないだろうか。
エンジニアの醍醐味は
コードの謎を解き、ほめ合う文化を作ること
ここからは、いったん「女性ならでは」の課題から離れて、エンジニアという仕事の楽しさそのものについて伺ってみよう。はたして返ってきた答えは、まさに「私という個人」、一人ひとりの個性を感じさせるものだった。
まず、樋口氏にとっての楽しさは「人との出会い」と「技術の進化」の2つだという。
「いろいろなバックグラウンドのある人たちと一緒に仕事をしながら、自分のエンジニアとしての知識や知見を広げていけるところがすごく楽しいです。あとは、どんどん新しい技術が出てくるので、そこに必死についていくという部分もエンジニアならではの面白さだと思っています」(樋口氏)
坂田氏が語るQAエンジニアの仕事の面白さは、まるで探偵小説のようだ。
「QAとして任される案件は、本当にコードだけあって仕様書が全然ないというフェーズが多いのです。それを一つひとつきちんと整理していって、もしかすると作った側も気付いていなかったような仕様を発見する。それを解き明かしていってきちんと検証に落とし込むプロセスは、自分でも結構好きだと思います」(坂田氏)
この「謎解き」の楽しさは、QAエンジニアならではの醍醐味だろう。単にバグを見つけるだけでなく、システムの本質を理解し、より良いものにしていく。そこには、開発とはまた異なった創造的な喜びがあるのだ。
そして、大森氏の答えはエンジニア文化の本質的な課題を突いており興味深い。
「楽しいと感じるのは、ほめられたときです。エンジニアって、あまりほめられないですよね。問題があったときには責められるけど、うまくいって当たり前という感じ。だから、もっとほめ合う文化、讃え合う文化、認め合う文化が必要だと思って、振り返り会でも意識的にそうするように心がけています」(大森氏)
「ほめられないなら、お互いにほめ合おう」。この大森氏の提案は、エンジニアの職場環境を改善する重要なヒントかもしれない。技術力だけでなく、お互いを認め合うコミュニケーション力も、これからのエンジニアには求められているのだ。
ライフイベントを見すえた会社選びが
安心して勤め続けられるカギ
女性エンジニアが避けて通れないのが、結婚・出産といったライフイベントとキャリアの両立だ。この点について、3人はどう考えているのだろうか。樋口氏は、現在の職場環境に大きな安心感を持っているという。
「もし自分が産休や育休を取って長期で休んだとしても、今の事業部は復帰後の自分の場所がきちんとあると思えるので、そんなに不安はありません。もちろん簡単ではありませんが、工夫次第で生活と仕事の両立は可能ではないかと思っています」(樋口氏)
坂田氏は、実際に子育てをしている人たちの姿から、将来のイメージを描くようにしているという。
「今のお客さんが30代半ばから後半の方が多くて、子どもさんの行事や病気で休まれるのを目にする機会も少なくありません。自分も将来的にはキャリアを目指す一方で、きちんと家庭のことも考えるというように、自分の意識を変えていく必要がありそうだと思っています」(坂田氏)
そして大森氏は、転職活動の時点で、すでにライフイベントへの対応を重視していたと明かす。
「実は転職の軸の1つに、自分のライフイベントの不安を払拭したいということも含んでいました。その点でレバテックは安心できることが入社を決めた理由です。現に社内では時短で活躍されている方も多いし、自分が1~2年後に子どもができたとしても、スムーズに引き継ぎをしてお休みに入って、また戻ってくるというビジョンが描けるので、今のところ特に不安はないですね」(大森氏)
3人に共通しているのは「企業選びの段階で将来を見据える」という戦略的な視点だ。これは、この先の転職を考える女性エンジニアにとって重要な示唆となる。ライフイベントは「いつか来る課題」ではなく、「今から準備できること」なのだ。
未来の女性エンジニアたちへ
「面白そうと感じたら、まず飛び込んでみよう」
最後に、これからエンジニアを目指す女性たちへ、現在活躍中の3人からメッセージをお願いしよう。樋口氏は、かつての「男性社会」のイメージにとらわれないことを強く勧める。
「昔は、エンジニアは男性社会というイメージが強かったのですが、今はまったくそんなこともなく、誰でも挑戦できます。自分のペースに合わせてスキルアップしていける、すごくいい職種だと思っているので、まずは飛び込んでみることが大事だと思います」(樋口氏)
一方、坂田氏は、エンジニアという職種の「働きやすさ」を強調する。
「エンジニアは副業から始められる方も多いですし、子育てしながらでもできる職種なので、興味を持ったら、まずはやってみて欲しいですね。あとはリモートワークが定着している職種でもあるので、そうした面でもかなり働きやすいのではないでしょうか」(坂田氏)
そして大森氏は、業界の現状から見た「今がチャンス」というメッセージを送る。
「エンジニア自体が常に人不足で、いろいろな会社が積極的に人を採用しています。それを追い風にすれば、未経験でも十分に今からスタートできます。私のように全く違う畑から来た人でも、自分のキャリア設計やライフワークバランスを考えながら働けるので、ぜひチャレンジしてみてください」(大森氏)
3人の言葉に共通しているのは、「完璧でなくて良い。まずは、始めてみよう」というメッセージだ。文系でも、農学部でも、プログラミング経験がなくても、興味や関心さえあれば、エンジニアへの道はいつでも開かれている。
* * * * *
IT業界は今、多様な視点と経験を持つ人材を求めている。女性ならではの視点が、新しいイノベーションを生む可能性もある。何より「ものづくりの楽しさ」を共有できる仲間が増えることを、現場のエンジニアたちは心から歓迎しているのだ。少しでも興味を持てたならば、その気持ちを大切に、ぜひ一歩を踏み出してみてはどうだろうか。
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- 経験者&採用担当者が語る「40代からの転職」~その傾向と対策
- キャリアに迷うすべての人へ ー40代からの生き方を語る「きのこカンファレンス」開催レポート
- 技術者としての成長と納得できる仕事の場を求めてmanebiに集まった3人のエンジニアたち
- データから読み解く! ITエンジニアの「市場価値」と「評価ポイント」
- 「富山への愛」から生まれた事業所ならではの自由闊達な雰囲気と抜群のチームワークが自慢(後編)
- 40代・50代エンジニアのための転職戦略とキャリア設計の考え方
- 走る!噛む!測る!Kinect for Windowsコンテストで飛び出した奇想天外なアイデアたち
- 男性向けレシピ動画メディア「GOHAN」はステップ1。動画マーケティング事業で更なるステップへ。|株式会社トピカ 麓 俊介
- Mozilla製品の普及に貢献した「ブラウザの母」が見据える、オープンソース文化の未来
- プロ意識を持って自らの成長プランを描く